恋しいレトロタイル風呂を訪ねて
昭和人間である私は、タイル風呂に郷愁を抱くのか、何故かとても惹かれます。
モザイクタイルの温泉を訪ねて、このサイトから始まり、侘寂温泉・ひなびた温泉の本からなど知った、レトロタイル温泉に出会えるのを、心ときめかしながら温泉旅をしています。
このサイトの中で取り上げられている、湯田中温泉の桃山風呂も立派なタイル風呂ですが、中でも特に心に残ったのが、鹿児島の江の島温泉でした。
そして今一番行きたいと思っているのが、和歌山の夏山温泉。名前だけでもアニメのジブリの様で夢がありますよね。夏山と書いてなっさと読むそうです。そこのもみじやさんですが、ずっとコロナで休業中で残念です。
今まで行った温泉旅の中で見てきた、レトロタイルの温泉をいくつか紹介させて頂きたいと思います。
また、皆様の中で「あそこにあったよー」というお薦めのレトロタイル風呂を是非ご紹介して頂ければと思います。
写真は鹿児島・江の島温泉
-
-
ナイス!

- 28
-
-
違反報告

161件のコメント
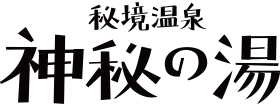
161.津軽の屏風山温泉(2度目登場)
青森の五能線木造駅には、巨大な縄文土器の人形が壁にデーンと張り付いている。その駅から徒歩でも可能だが親切に送迎してくれるのは、屏風山温泉の2代目ご主人でまだお若い。
青森は巨大簡素浴場が多く、此処もその一つではあるが、大きなタイル風呂を2つと寝湯を1つ、水風呂も備わっており、この水風呂と温泉との交互浴が実に気持ち良い。
井戸水に源泉を加えており、冬場でも置かれている。流石に冬は入るのに少し勇気が要ったが、浸かるとやっぱり気持ち良かった。
やや熱めのナトリウム泉は湧出量も多く、各部屋にも家族風呂として温泉が引き込まれている。
こちらの浴槽も小丸タイルで造られていた。
素泊まりで客室温泉付きという宿は、私は此処と鹿児島の市比野温泉丸山温泉しか知らないが、実に有難く良いものである。
冬は24時間かけ流しているので、いつでも好きな時に自由に我が部屋の温泉に入れるのだ。
これで4400円!温泉で床暖房されているので非常に温かく快適に過ごせ、部屋にはWi-Fi、冷凍冷蔵庫、テレビ、水洗トイレ、洗面所、エアコン、浴衣、タオル類、歯ブラシ付きで、廊下にフリードリンクコーナーがある。
食事も付けられるが、出前も頼めるし、近くにスーパーもあるという非常に便利で快適リーズナブルな温泉宿であり、連泊してももっと居たいと思わせる温泉宿であった。
画像1.部屋風呂 2.3大浴場
160.大鰐温泉河鹿荘
青森の大鰐温泉民宿河鹿荘。午前中に到着してしまったが快く部屋に通して下さった。
温泉は集中管理されており、そこからの引湯。白丸レトロタイルが用いられた浴槽。
温泉街にはリアルな大鰐モニュメントが。名物は30~40センチある大鰐温泉もやし。また、駅前カフェのFromOでは昼はサンドイッチが、夜はパスタやピザが美味しい。
159.湯田川温泉理大夫
湯田川温泉正面湯の前に理大夫旅館がある。
湯田川温泉郷の宿はいずれも小綺麗な感じである。
理大夫旅館では、湯縁が大理石で造られた円形浴槽の雰囲気が良い。それとは別に角の貸切風呂もある。
部屋は二間在りとても快適に過ごせる温泉宿ではあった。
158.芦ノ牧ドライブ温泉
詫寂温泉本に載せられていたレトロタイル風呂。
ドライブインと言うよりも超古い土産物屋さんが店の隣で営業している温泉で、オープンと同時に男性客が1,2組現れた。
浴槽は縁のみがレトロタイル使いが残っており、浴槽内のタイルは新しい。
一部には、レトロタイルの蒼い色が滲んだ様な?不思議タイルが用いられていた。
157.鶯宿温泉小枝旅館
鶯宿温泉郷には多くのレトロタイル風呂を持つ宿がまだ残っているが、石塚旅館と民宿煙山は残念ながら閉業されてしまった。
いくつか残る温泉宿の内、外観の色タイルも濃い原色であるため今まで避けていた小枝旅館に入ってみた。
予想とは違い、使われているタイルの色そのものは紺色や赤等であるが、全体的な雰囲気がシックである。
カラーガラスの窓は昭和感に溢れ、濃い色のタイル浴室に良く似合っている。
男女別浴室では若干造りが違い、広めの男性浴室の方が雰囲気が良かった。
玄関口では地元の常連さん達の井戸端会議が行われていた。馴染みの欠かせない温泉なのであろう。
また訪れてみても良いかも知れない。
156.松之山温泉みよしや
日本三大薬湯となっている松之山温泉。中でもみよしやの温泉は素晴らしい。
一度タンクに貯められてはいる(集中管理)が、源泉湧出個所に近いためか新鮮な源泉は濃厚でとろみを持ち、稀に見る高濃度のメタケイ酸含有量であり、保湿作用が強く肌はいつまでたっても滑らかスベスベであった。
浴槽はレトロタイルとは言えないが、赤茶色のタイルがコントラストとして使われた、くっきりした色合いの湯船である。
素泊まり専門宿だが、館内の清潔さにはおそらく定評があるだろう。近くには食事処もあるため連泊をしたい温泉宿である。
155.下部温泉湯元ホテル
冷泉で有名な下部温泉。中でも湯元と名乗っているだけあり、湯元ホテルの源泉は岩場からの自然湧出している冷泉・霊泉である。
湯舟は昔のままのレトロタイル風呂であり、幾つかの浴槽がある。
154.羽沢温泉松葉荘(2度目の登場)
3軒の羽沢温泉の内、一番源泉湧出個所に近いのが松葉荘で、加温加水無く源泉の湯温のままで良質な温泉が楽しめる。
豆タイルではないが、マットな白の角タイルはレトロモダン感があり、湯船の周りの床板とも良く合っている。
泉質は極上!で、宿はアットホームで有りながら料理も良く、リピーターが多い。何度でも行きたくなる、何度行っても良い温泉宿である。
153.羽沢温泉紅葉館
羽沢温泉には3軒の宿が在り、内2軒がタイル風呂。
源泉湧出個所が松葉壮に一番近く、紅葉館では加温が必要なため、どうしてもその分宿泊代も高くなる。
女性は円形、男性は瓢箪型の浴槽で、丸い風呂はやはり可愛い感じがする。
152.市比野温泉共同浴場昭和湯
市比野温泉昭和湯、名前もそのものであり、浴槽も昔ながらのタイル風呂のままだった。
湯縁を少しへこませて、そこから排水されて行くというシンプルな湯舟。
簡素ながらも味わいがあった。
訪れる人も少なく、少しわかりにくい場所に在った。
151.市比野温泉の洋菓子店で温泉
市比野温泉街の老舗洋菓子店では、日帰り入浴ができる。
お菓子は買っても買わなくても温泉だけでもOK.
穴場のタイル風呂なのかも?
150.美しい市比野温泉丸山温泉(2度目の登場)
鹿児島にある市比野温泉の中にある丸山温泉。
浴槽内だけでなく湯縁から床まで、完全にレトロタイルが用いられたままで残されている温泉は珍しく貴重である。
明るい日差しの中、男性浴室は水色系タイル、女性はピンク系タイルで造られた浴槽はとても可愛く美しい。
このままのタイル浴槽がいつまで使えるのかは解らないが、熱めの温泉に浸かりながら時の経過を感じられる、ノスタルジック感ある癒し系レトロ風呂。
写真は男性浴槽、他に貸切風呂もありそちらもタイル浴槽である。
日帰り入浴でも宿泊でも利用可。
素泊まりに於いて、部屋に家族風呂が付いている宿は数少ない。私が知っている限りでは此処と、青森の屏風山温泉だけ。
149.山梨湯村温泉旅館明治休業中
この宿の浴室にしかない、貴重なガラスブロックタイルの明かりが湯に反映し、黄金風呂の様に温泉が輝いていた、山梨湯村温泉旅館明治の女性浴室。
私の大好きなこの湯舟には、2022年の年末に年納温泉として訪れたのが最後だった。
また訪れたいと再三電話しても繋がらず。観光協会へ電話して解ったのが、春頃より来年頃までリニューアル予定で休業中との事だった。
そうか‥「旅館業は大変だし、1人息子は継いでくれるかどうか解らないし」と女将さんは話されていたので、閉業されたのかと観光協会に確認したが「そんなことはありませんよ」と言われたので、もしかしたら息子さんが継いで下さる事になり、それで全面改装されるのかも知れないなとも思ったりしてほっとしてはいる。
女性浴室のライトが少しずつ途絶え、黄金風呂が暗くなっていくのが気になって仕方が無く、どうなっていくのかなあ?間接照明にでもしてくれればいいんじゃないのかなあ?と気がかりな私に「古くて修理しないといけない所は一杯あるから、一つずつ手を付けただけでは収まらないから」と、女将さんはそう言われていたっけ。
温泉がとても素晴らしいから辞めないで欲しいと言う私に「う~んそうなんだけど・・」とも。
全面改装に踏み切られて、またこの先あの極上の温泉に入れるのは嬉しいし、経営者が変わる事無くあの旅館明治が続いて行ってくれればこれ程嬉しいことは無い。
ただあのガラスブロックタイルの壁は・・女将さんに「全国の温泉周ってもあのガラスタイルの温泉は何処にも無い、本当に貴重な物だから!」と切に訴えたけれども・・
コンクリート壁とガラスタイル壁の間に電気が燈っているので、修理が非常に困難というかできないような造りであり、逆に言えばよくぞ今まで持ってくれたという様な代物だったのかも知れない。
もしもあのガラスタイルを残してくれたとしても、今と同じ造りは無いだろう。
どういった形であっても、何処かに取り入れて貰えたら良いのだがと思うが・・。
男性浴室の方は、比較的新しく広く綺麗なタイル浴場だったので、もしかしたらそのまま使われるのかも知れない。
湯村温泉街は、昭和レトロな雰囲気を僅かにでも残している温泉であり、大型ホテルと旅館が混在しており、各宿が自家源泉を持っている。だからお湯が良い。その中でも特に旅館明治の温泉は、40℃~41℃程の温湯で柔らかい極上の温泉だった。
新しく建物が生まれ変わっても、あのひょうひょうとしてちょっとユニークなご主人と、庶民的で明るく気さくな女将さんに、変わらず出迎えて貰いたいし、そこにもしかして息子さんが加わり、2代であの温泉を守って行ってもらえるなら最高である。
148.大正建築におもてなしが光る、市比野温泉みどり屋旅館
写真
①川向うから見る宿と小滝。川沿いには、ねむの木の花と紫陽花が咲き、時折青鷺が訪れる。
②レトロな館内。
③3階の与謝野晶子と鉄幹が泊まった部屋に通された。
改装された男子トイレには、短歌の名手の女将さんが書かれた張り紙が。
「いそぐとも 心静かに 手を添えて
外にこぼすな 松茸の露」
147.大正建築の宿で掛け干し米の釜炊きを!おもてなしが光る宿
レトロタイル風呂が多く残る鹿児島県北薩摩にある市比野温泉。その温泉郷のシンボル的存在が、大正建築のままで残っているみどり屋旅館で、与謝野晶子と鉄幹が泊まった宿である。
今も川向こうから見ると橋のたもとに、灰色となった木造3階建ての建物が見え、寂れてしまった市比野温泉街の此処だけが、情緒ある雰囲気を感じるスポットでもある。
6月の蒸し暑い日に到着したが、案内して貰った角部屋は障子が開け放たれ、階下には小滝が見え時折青鷺が飛来している。
眺めが良く明るい角部屋乍らに、とても涼しく心地良い。何故に?と思ったらエアコンが付けられ、扇風機が涼風を送っている。
まず、この様な勿体ないくらいのおもてなしを受け、感激した事から始まったのだった。
「もう歳なので・・主人も80歳を過ぎているんですよ。でも料理だけはしっかり作りますから」と高齢になられたご夫婦で営まれる宿は、1日1組限定宿泊とされている。
「1人でも2人でも家族でも1組です」という事で、お風呂は常に貸切状態で気兼ねせず、好きな時間に何度でも入れるとい事だ。
こちらの風呂は円形と四角の浴槽が在るが、主に用いられているのは円形風呂である様だ。
「丸いのって珍しいそうですね」と女将さんが言われるので「はい丸いお風呂は可愛らしいけれど少ないですね。やはり作るのに手間がかかるからでしょうか?古いタイルで造られたお風呂自体が残された物だけになっているので、珍しくなって行くだろうと思います。もう在るだけですから。タイル自体が作られていないし、一つ一つ手貼りで造ってくれる職人さんもいませんから、とても貴重なのですよ。そしてこのお宿は何と言っても大正期の建物ですから。有形登録文化財として残っている建物自体が少ないですのに、とても素晴らしい事です」とお話しすると、市比野温泉の多くの宿が廃業となってしまった寂しさや、どうしたらこの温泉街を盛り上げて行けるだろうかと模索中である事や、地域に溶け込んで助け合って暮らしているという、地元の繋がりを伺う事ができた。
市比野温泉郷に大型ホテルが建ち始めた時、温泉が枯渇してしまう事を心配し、小旅館が持っていた自家源泉を集中管理する事にし、温泉を確保するため組合源泉とした事。「もうそのホテルはみんな潰れていまいましたけどね。うちもボコボコと下から湧いてたんですけど」と残念がられる。
なので、市比野温泉は組合源泉であり、5本の源泉をタンクに管理し配湯しているそうだ。
夕食前にその丸いお風呂の温泉に浸かる。熱いが気持ち良い温泉である。
広めで天井が高く明るい浴室の床や湯舟は総レトロタイルで造られ、観葉植物が置かれているのも、女将さんのおもてなしの1つなのだろう。
そして何よりも光るおもてなしが、1人用の釜で炊かれた炊き立てのご飯が、朝夕食事に出されると言う事だ。2合程もあるだろうか?真っ白で光るお米は、食べたら軽く、そして当たり前だがとても美味しい。
女将さんが「掛け干し米なんですよ。近くで作っている方から頂いて」と言われるそのお米は、釜炊きというだけでも珍しいが、今では貴重な掛け干し米なのだった。
旅していると稀に見る。私たちが子供の頃は当たり前の風景でもあった、稲刈りの後、竿に干された稲穂が並ぶ光景は、今では稀にしか見られなくなり、そのお米が自分の口に入る事は無い。
それを今口にできているという喜びと、何より美味しさに、此処でしか食べられないお焦げの香ばしさに、そしてそれが夕に朝にと炊き立てで出して下さったという、おもてなしに感動するほかなかった。
厨房に立つご主人は、凛とし白い帽子をかぶり、女将さんは白く長いビニールのエプロン姿で、汗をかきかき食事の用意をして下さっていた。
たった1人の客のために。
寝床では滝の川音を聞きながらも、清潔な真っ白のシーツで快適に眠りについた。そして熱めの朝風呂はとても気持ち良かった。
トイレだけが共同だが、改装されておりウオシュレットトイレまで用意して下さっていた。
この古いお宿でのトイレ改修は容易ではないと思うが、客の事をひたすら考えての、大切なおもてなしの一つと捉えて下さったからなのでは無いだろうか。
これで、1人泊2食付き何と6850円だった。だったとしか書きようが無い。
女将さんは、徒歩で20分もかからないバス停だが、車で送って下さると言う。
「温泉だけはいいんですよ」と謙遜されながら話されるが、これ程おもてなしを大切にされるお宿には出会った事は無い。
もうこうなると商売とかそんな事ではなく、このお宿を愛し、客を愛し、地域の人を愛し、ただそれだけでお宿を続けて下さっているとしか思えなかった。
是非、連泊させて頂きたいお宿である。
146.鶯宿温泉トルコブルーのタイル風呂が素晴らしい宿に宿泊してみた
岩手県雫石にある鶯宿温泉は、レトロタイルが多く残る温泉郷であり、中でも珍しく全てのタイルがトルコブルーで統一されているという、美しい湯船を持つ民宿とちないに今回は宿泊してみた。
今では作られなくなった豆タイル。それを職人さんのセンスと手張りで一つ一つが張られ造られた、色も容も違うレトロタイル浴槽。それらは一つ一つが全て違い、同じものが二つと無い。在るのかも知れないが出会った事が無い。
もう再現されることも無く、失って行くだけのレトロタイル風呂は、銭湯に多く見られ、古い温泉宿に見られ、温泉郷としては鹿児島・川内高城温泉郷や日当山温泉郷、市比野温泉郷、福島・飯坂温泉郷、中でもこの鶯宿温泉郷に多く残されていた。
そしてこの民宿とちないのタイル風呂は、目が覚める様なターコイズ(トルコ)ブルーの小丸タイルで、よく見ると青緑色であったり碧だけであったりと、微妙に色に変化がある違ったタイルが用いられている。
そしてその中でも特に目を引くのが、以前も書かせて貰ったが排水溝の部分で、奥まって行く排水溝の円筒にまで見事に丸いタイルが貼られており、目が釘付けになってしまう。
この湯舟の美しさは、一体どんな方がこのタイルを選び、一体どんな職人さんが造られたものなのだろう?
お宿のご主人にも女将さんにもお尋ねしてもよく解らない。おそらく昭和40年台頃のタイル風呂であろうとは思われるが・・。他の鶯宿温泉のお宿と時を同じくして造られた物であろうが・・とにかくため息が出るくらい美しい湯船である。
そして温泉も実に気持ち良い。鶯宿では一番多くの宿が用いている杉の根源泉だが、川向うにその源泉が在り比較的源泉に近いためか?一度タンクに貯めているとは言え、湯華も舞い温泉の香りもする。
湯底注入の槽内排水であるためか、温泉に新鮮さが有り、熱めだが非常に気持ちが良い温泉である。というのは以前にも感じていた。
そして今回宿泊を決めたのは、この綺麗なタイル風呂ともう一つは接客にあった。
特に日帰り入浴をうたってはいない宿であるため、必ず確認が必要であったが、そうして訪れた際の丁寧で親切な接客に、料理も良いと感じたのだった。
もうそれは直感でしかなかったが、どうも親切できちんとした対応のお宿は、料理までもきちんと美味しい様に感じてしまう。
そして、それは当たった。申し訳ないくらい一品一品手をかけた、私の嗜好に合った品を用意して頂き、感激一塩だったのだ。
女将さんが「主人はこうして一杯出すのが好きなんですよ」と言われるままの沢山のご馳走が並び、これで通常2食付き1人泊7400円程の宿泊代が、更に予約時にご主人の方から岩手割が利用できる事をおっしゃって下さり、クーポンが貰え実質4000円程で宿泊できたのだった。
3階建ての宿であり、3階が浴室になり、2階が客室で1階が食事処となっており、女将さんが「私と一緒で宿も古くて階段が大変で、お食事は1階になりますが」と言われたが、何のその客室に入ってびっくりした。
綺麗な広い部屋に布団が敷かれ、広い間口にはソファが置かれ、勿論エアコン・テレビ・冷蔵庫・Wi-Fi完備で、このソファが実に座り心地が良くとても快適な部屋だった。
女将さんが「もう風呂も古くて私と一緒で」と言われるので「女将さんと一緒のとっても綺麗なタイル風呂で、とっても貴重ですよ」とお返しした。
鶯宿温泉郷は湯量が豊富で多くの宿が在り、大型ホテルと極端な小旅館・民宿が混在し、中には廃業した宿も見られるが、暗さを感じさせないどちらかと言うと開放的で静かなのんびりした温泉地の様にも感じる。徒歩圏内で温泉巡りができるが、温泉郷自体は横に長く距離がある。
梅に鴬から始まった鶯宿温泉である様だが、春は桜も多く、その前には土手にカタクリが群生するのが見られる。
源泉は熱めで集中管理され配湯の宿が殆どであるが、宿により泉質に差があるという事も頭に置きながら、一つ一つの湯船と温泉を楽しんで頂きたい。
お宿として選ばれる時はお料理や快適さも考慮して、お勧めはこの民宿とちないと鶯泉館であるが、鶯泉館は更にリーズナブル価格でお料理も驚く程だが、ビジネスで利用されている事が多く、平日は満室となり土日なら宿泊可能だが、部屋にエアコンが無いとの事で夏場は厳しいかも?
また、あの小学校の校舎の様な郷愁ある石塚旅館は閉業となったようで、昨年の春無理にお願いして日帰り入浴をさせて頂いた事を感謝致します。
145.長野・大塩温泉旭館
大塩温泉と書かれた看板を目印に田舎道を入ると、廃屋の温泉宿が並んだその奥に、1軒旭館と看板を出した雰囲気の良い宿が見えほっとする。
大塩温泉と聞き勝手にナトリウム泉かと思っていたが、実はラジウム泉であり、更に38℃源泉のぬるゆであるため、冬季は加温が必要な事とコロナが重なって、3年間は休業されていたようだ。
常連さん達の要望を受け要約4月から再開されたが、まだ宿泊営業だけとの事であったが、遠方からと聞いてご主人は特別に日帰り入浴を受け入れて下さった。
1つの浴室しかなく、レトロタイルの大浴槽にくっ付いて造られた、扇形の小浴槽は加温槽なのだがこちらは空であった。源泉槽1本での営業であり、おそらく冬季は休業となるのかも知れない?
浴槽内のタイルは水色の大角タイルなのだが、大浴槽の湯縁は主に黒の細長タイルで造られていて、加温槽などは丸タイルも混ざっていたり、浴槽のつなぎ目は床のタイルが使われていたり、それに広い床の豆タイルも色が不揃いで、つぎはぎ感が何とも気取っていないレトロなタイル浴室と言うか・・もしかしてご主人が貼ったとか?!
その大浴槽には、タイルの色により水色に見える透明で綺麗な源泉が掛け流されており、飲泉コップも置かれレトロ感を増していた。
何より大きく書かれた温泉の効能書きが良い。本当に効きそうな感じがし、ご主人の人柄と併せて宿泊したいと思ってしまったし、是非この温泉と浴室を守って行って頂きたいと願った。
144.長野霊泉寺温泉③中屋旅館
ぬるゆ霊泉寺温泉タイル風呂の3軒め中屋旅館は、宿の外観及び館内は一番レトロ感がある。
温泉は、朱色が褪せた様な色の湯縁に、槽内は水色のレトロタイルを使った変形長方形の浴槽に、細い筒から少量の投入で、水位は湯縁から10㎝以上したであり、溢れ出す事などある筈もなく循環だと思ったが?
HPでは源泉かけ流しとなっている様で、加温時期は溢れる程の湯量が無い?となると溜まり湯という事にもなってしまうし・・?よく解らない感じだ。
ただ、男女の浴槽は壁を仕切りにし繋がっている様子だった。
浴室の床は黒色っぽいタイルで、男性浴槽は色違いのタイルなのかと思ったが、女性浴槽と全く同じ色・造りだった。
日帰り入浴ではこの男女別浴室の利用だけだが、宿泊すると笹船の湯という貸切風呂を利用でき、こちらは黒っぽいレトロタイル造りの笹船型浴槽である。
143.長野霊泉寺温泉②松屋旅館
ぬるゆ霊泉寺温泉の松屋旅館は、霊泉寺43℃源泉の湧出場所に近い宿ではあるが、日帰り入浴で訪れた3月下旬はまだ加温されていた。
加温かけ流しであるにも関わらずその投入量がザバザバで、やはり大きめの湯船にドバドバ源泉というのは本当に気持ちの良いものだ。
浴槽の縁は石であるが、浴槽内は緑を帯びた青いタイルの色が、温泉の揺らぎと共に光の加減で微妙に全体の色が変わり美しかった。
日帰り入浴を受け入れて頂いた時間帯は、宿泊客が訪れる前であったため貸切状態で温泉を利用できたが、宿泊しても男女別の浴室としての利用となる。
日帰り入浴の受け入れは、この時期加温しているため時間帯や日にちが限定しており、よく問い合わせてから訪れる必要がある。
加温の必要が無い季節になれば、いつでも日帰り入浴可能となるのかも知れない。
源泉湧出個所は共同浴場が一番近いそうで、松屋旅館は共同湯の隣に在る。
共同湯の浴槽はリニューアルされ、タイルは全く新しい物に造り替えられていた。浴槽は非常に浅い造りの湯船で、皆が半寝湯状態で入らなければならない様な何だか風変りな浴槽だった。
142.長野霊泉寺温泉①遊楽
ぬる湯の霊泉寺温泉には現在4件の宿が在り、そのうちの3軒がレトロタイル風呂を持つ。
宿泊先に選んだのは遊楽という小宿で、2つの浴室を持つ。というか、一般的には小浴槽が女性用で、大浴槽が男性用。もしくは家族風呂として小浴室を利用しているようだ。
この時は宿泊客が2組だったので、それぞれの浴室を貸し切りとして利用する事になった。
先に宿に付いたので、大浴場の方を利用させて貰った。というか、利用して於いて良かった。でないと大浴場へは入れることはなかっただろう。
というのも「空いている時に貸切中にして入って下さい」という自由セルフ方法で入浴となると、これがまたたった2組の客といえど、入りたい時間が全くの様に重なってしまうのだ。タッチの差でも先に入った者勝ちとなる。
これが浴室が1つしか無いと最悪で、ため息ばかりつく事になったことがある。
遊楽は一応2つ在ったが、結局は相手方はご夫婦で私は1人という事で、恒に小浴室しか空いておらずという事になってしまったのだった。
「宿泊は2組だけですから」と言われてもなかなか思うようには入れないのが現状である。
温泉は単純アルカリ泉。浴槽内は共に水色角タイルで、大浴槽は丸角の長方形で湯縁は青のレトロタイル。源泉投入口が獅子舞?かと思ったが龍の様であり、割と珍しい。
小浴槽は扇形で、投入口は真っ黒い岩だった。これは温泉成分のためなのだろうか?湯縁も紅色レトロタイルなのだがほぼ黒くなっていた。
3月下旬では43℃の源泉を宿まで引湯して来ると湯温が下がり、加温かけ流しでの提供だが、もう少し暑くなってくると源泉のままでの入浴となるそうだ。
手作りの料理が美味しく、和洋折衷といった感じで「ビーフシチューも作ってみたから」と出してくれたり、何よりおひつの蓋を開けたら赤飯だった事が嬉しかった。何か理由があるのか尋ねてみたら、何もなく季節に応じて山菜ご飯になったり、きのこの炊き込みご飯になったりするそうで、女将さんはお料理がお好きなのだそうだ。このお宿を選んで良かったと思った。やはり宿泊するなら料理が美味しい宿が楽しみである。
141.P.S土肥温泉民宿山仙の漁港風景
土肥漁港の夕景写真
140.伊那・鹿塩温泉塩湯荘
大鹿村風景
139.伊那・鹿塩温泉塩湯荘
宿風景
138.長野・伊那大鹿村、鹿塩温泉塩湯荘
飯田線に乗り伊那大島駅で下車し、1日1本のバスに乗り鹿塩温泉へ。という予定が、列車の車窓から左右の中央アルプスと南アルプスをキョロキョロし、駅名を聞き間違え慌てて伊那田島駅で下車してしまった。列車は1時間後に有るけれどバスが無い!
慌てて宿に電話したら「調度そちらの方へ買い物に出かけているから迎えに行きますから待っていて下さい」と何と嬉しいお言葉が。
以前にもあったっけ・・あの時も1時間以上かけて迎えに来て貰った事が・・。
列車で移動していると、車に助けられる事があると本当に本当に嬉しい。
おまけに迎えに来てくれた若女将さんは、久々に晴れたからとこの地域の桜の名所、南アルプスを臨む大西公園へも寄り道をして下さり、その美しい風景を見せて下さった。
この公園は慰霊で植えられた桜が育ち、そして現在は小学校を卒業して行く子供たち一人一人が、自分の名と共に桜木の植樹をしているという事を聞き、とても地元愛溢れる公園だなと思った。
若女将さんの接客は丁寧で優しく、大鹿村の事を色々お話をして下さりながら塩湯荘へ到着。
ご主人と大女将さんとの家族経営のお宿であり、看板犬のとても人なっこい雪ちゃんというスピッツもいた。
温泉は9.5度の冷鉱泉を加温したもので、僅かだが掛け流されている。
浴室が1つだけなので、この日はもう一組のお客さんと時間調整をしながら貸し切りで入浴となった。
薄ピンク色のタイルで造られた円形の浴槽に、槽内が水色タイルのため湯がやや青っぽく見え綺麗で、とても可愛い感じの湯船である。
泉質はナトリウム・塩化物冷鉱泉で、唇に付着するととてもしょっぱく、何と成分総計が22,802㎎というとてつもない濃度で、青みがかった湯がとろりと揺れている様が美しい。
湯気に包まれた浴室の和かい雰囲気に、ぼうっとした穏やかさが漂い、ほっと心和む浴室であった。
ゆっくり浸かっていたいが非常に良く温まり、そして浴後どっと疲れ、指はカサカサになっていた(帰宅後はツルツルになっていたけれど)
伊那大鹿村は「日本の最も美しい村連合」に入っており、宿は自然あふれる里山に在り、宿の前には渓流釣りができる美しい川が流れ、山沿いに所々建ち並ぶ民家には花桃の木が植えられていた。
朝一温泉で身体を温めた後は、朝食までの時間里山散歩を楽しんだ。
帰りは、お茶菓子で出された塩最中が大変美味しかったので買って、鹿塩温泉バス停から伊那大島駅行のバスに乗る。
ダム湖沿いに走るバスの車窓からは、桜から花桃へそして芽生え始めた新緑へと、移ろう景色を目にしながら大鹿村をあとにした。
137.伊豆・大沢温泉野天風呂山の家にあった内風呂
大沢温泉山の家は露天風呂しかないのかと思っていたが、内湯も在り日帰り入浴でも入る事ができると聞き訪問。
宿泊は素泊まりのみで、宿泊棟は温泉とは少し離れた場所に建てられていた。
内湯は主に泊まりの方が予約を入れ、貸切で利用されているため、日帰り入浴では入られない事が多い様だった。別料金が必要で、古くレトロな休憩室がある。
私も希望したが空いていなかったので、どんなのか見せて欲しいと頼み、僅かの隙に見せてだけ貰ったら、何と湯船にレトロタイルが使われていたのだった。
湯縁は石で湯底は新しい大きなタイルだが、槽内がブルーのレトロタイルで、その色がとても美しくもう少し見ていたかったし、勿論浸かりたかったのだが残念だった。
136.土肥温泉民宿山仙のタイル風呂と美味しい食事
伊豆の土肥温泉にも小さなタイル風呂が在りました。民宿山仙は予約時からの電話対応がとても優しく親切で、訪れる前から安心して楽しみにできたお宿です。
小さな温泉民宿に何とお風呂が3つもあり、必ず何処かが空いているので待つことはありません。
その内の2つがレトロタイル風呂で、湯船は小さいですが貸切で浸かれます。
この頃貸切風呂を利用する事が多く、小さいけれどやはり貸切はいいなあと思います。
タイル風呂1つ目の浴室は、湯縁と槽内が黒の角タイル、湯底と浴室の床が紺の丸タイルというシックな感じ。
2つ目の浴室の方がレトロ感があり、紺系と水色の豆タイルや角タイルで造られており、湯船の角が丸みを帯びた感じや、富士山のタイル画がレトロな雰囲気を演出していました。
ちなみにもう一つは露天風呂という名ではありますが、囲まれた天井の素材と隙間が多いからそういう名にしているのかなとは思いますが、こちらは石造りの浴槽でした。
伊豆の温泉の多くが、カルシウム・ナトリウム・硫酸塩泉で、透明な直ぐ温まる温泉です。そのため長くは浸かっては居られませんでしたが、かけ流しで気持ちの良い温泉です。
料理も良く、写真の夕食は2名分ですが、エビフライや舟盛が付き、キンメダイの煮付けは小さかったですが美味しく、鍋には大きな浅利が入り、茶わん蒸し、更に特注で伊勢海老のお造りを付けて貰いました。
朝食には鰺の干物に、伊勢海老の頭を味噌汁に仕立てて貰い大満足。これで1人泊2食付きで10000円でした。
料理、接客、3つ在る温泉浴室、いずれも小さな温泉民宿でありながらとても心地良く、また宿から直ぐ近くに漁港や浜があり、埠頭から見る夕陽は素晴らしく、夕陽が沈んだあと漁港が薄紅色に染まる風景も美しく、これら全てが思い出に残る旅となりました。
135.伊東温泉のゲストハウスに在ったタイル風呂
伊東温泉の高台というか、駅からはタクシーでないと登って行けないような坂道を延々と登った所に在るゲストハウス倭(ヤマト)荘は、2018年にリニューアルオープンした宿であり、浴室は以前からのものが2つと新しく追加したものが1つで、昔からのものがタイル風呂として残っていた。3つの浴室はいずれも小さく、貸切風呂として利用。
ゲストハウスに、昭和のレトロタイル風呂が存在していた事自体が意外であったが、2つのタイル風呂の中でも1つが、レトロ感が残る総豆タイル浴室のままだった。
黒の角タイルと水色の丸・角タイルで統一され、スッキリ感がある湯舟と浴室は小さいながら明るい。
源泉投入口は水道の蛇口からで、口先は析出物で白くなっていた。
伊東温泉の源泉は熱いが、セルフで自動調整しながら源泉かけ流しの湯に浸かると、熱いながらも気持ち良かった。
屋上に出ると、夜は街の夜景や星空。夕陽・朝陽は臨めないが、日の出前には一斉に鳥たちが鳴きだし、色んな鳥の鳴き声が反響し大音響だったが、朝陽が昇り出すにつれ静まって行き、後は鴬の鳴き声だけが続いていた。
アレは何だったんだろう?鳥たちが朝の挨拶を交わし合っていたのだろうか?
伊東は町の様でも有るが、まだ多くの自然も残されている。伊豆半島は素晴らしい温泉地である。
134.民宿500マイルのタイル風呂
虎杖浜温泉にはまだいくつかのタイル風呂が残されており、民宿500マイルは露天風呂が有名だが、2つある内湯の1つの方は何とレトロタイルが使用されていた。
特に目に付いたのは、白い目地に青丸タイルを手で一つずつ埋め込んで、サイコロの五の目模様にしていた部分で、ナイスセンスだと思った。
始め見た時はそういう絵柄タイルなのかと思ったが、よく見ると白目地を生かして、タイルを手で埋め込んでデザインされたものだと判った。
それらが浴槽の周りの壁にズラッと並び、湯船にも水鏡になり浮かんでいる。
浴槽内は青丸タイルがびっしりと並び、サイコロ模様のタイルがアクセントになっており、楽しい湯船だった。
もう一つの内湯はバリアフリー対応の普通のもの。
民宿500マイルは露天風呂が大変気持ち良く、同源泉の内湯は少し熱く感じるかも知れないが、温泉自体がヌルヌルの非常に気持ち良い温泉で、日帰り入浴でも貸切対応なので時間があれば内湯も入ってみて頂ければと思う。
133.羊と牛?の投入口
長野・鹿教湯温泉は1日10万トンの湯量を誇り、各宿へ組合源泉が供給されている。
今回宿泊したのはふぢや旅館で、鹿教湯温泉共同湯・文殊の湯に近い源泉かけ流しの、かなり古い建物の宿である。
玄関を入ると、湿気臭さと僅かなカビ臭さがマスク越しに伝わって来て、宿の古さを思わせた。
案内された部屋は三階でエレベーターはある。当然古い部屋にはテントウ虫まがいの虫がいたり、出てきたりした。
古いファンヒーターしかなく、消したり消えたりすると凄く臭く、煙までは出なかったがおそらくかなり空気は汚れているだろう。
トイレは当然の和式と、洋式もあったが狭すぎるし・・。
洗面所の水を出すと茶色く濁り(何処かに山の美味しい水だと書いてあったが)温泉(飲泉ができる温泉らしい)と書かれた蛇口からは、ぬるく薄茶色の温泉水が出てきて、これを飲泉したら大変な事になるだろう。
食事は地味で味付けも悪い。Wi-Fiはかなり弱くほぼ入らない。
そして夜には突如と電気が切れた。しかも二度も。しばらくして付いたがその原因が解らないという。その度にファンヒーターも切れ、臭くて困った。
部屋からの眺めとしては、真ん前に廃墟となった建物の崩れた壁が見えるし、横に目をやると観光スポットなのだが四月上旬では枯れ木で寒々しいし、前方にはこの地に似つかわしくない高層ホテルが建ち、温泉プールが見えていた。
何故この宿を選んだか、勿論レトロタイル風呂があるからで、その期待の湯船は露天風呂に在った。
床全面、湯縁、2つの湯船、それら全てがレトロタイルでできていた。
投入口だけは旁替えたそうで、新しい感じの石造りだったが、長方形と扇形の2つの湯船は、昔からのものがそのままで残っていた。
長方形の湯船は、湯底が黄緑色のタイルで造られ、そのためか湯は明るいグリーンに見え、側面のタイルは白であるがこれまでも薄青く見えていた。
単純泉だが露天風呂に於いては、微かに焦げた様な温泉らしい香りがどことなくし、やはり露天風呂というものは気持ちの良いものだ。
男女別に1時間ごとの細かい時間制限が設けられているため、日帰り入浴では注意が必要。
また露天風呂の看板が出ていないため何処にあるのか解りづらい。
地下に全ての浴場があり、露天風呂はエレベーター前方にある階段を数段上がった右手が、入り口になっている。
内湯は女性用と共同用に分かれており、共同用というのは男性用ではなく、混浴と言う事であるが、宿泊客がおそらく私しか居なかったので、共同湯にも入れた。
目を引くのが源泉投入口で、女性用の浴室には析出物で上手く白くなった羊と、共同用浴室では、細めで怖い目をしたおそらく牛?の投入口があり、羊も牛も珍しい。
女性用浴槽は小さく、湯底には深緑系の豆タイルが敷き詰められていた。
共同用の浴槽はとても大きく、ブルー系の豆タイルが敷き詰められ、浴室は明るかった。共に湯縁は黒い石である。
泉質は単純泉ではあるが、白い析出物が投入口にいくらか付着し、非常に良く温まるのは、ラジウムを含んだ源泉が混じってるためだそうだ。またぬるくするため、大塩温泉の源泉も加えられ、5本ほどの源泉が一度タンクに溜められてから配湯されているそうだ。
鹿教湯温泉には他にもタイル風呂を持つ宿があるので、またの機会に訪れたいと思う。できれば新緑か紅葉時期が良いだろう。
132.下諏訪温泉、家族中心の宿
前回宿泊した下諏訪温泉の宿は「宿中心」と書かせて貰ったが、今回の下諏訪温泉中川旅館は「家族中心」の宿と、書かせて頂きたい。
スポーツ合宿等での利用が多い様であり、一般的な旅館としては目立たない風の宿である。
玄関口は2つあり、上の入り口扉を開けたら下駄箱にスニーカーがずらっと並んでいた。
階下が個人客の玄関口の様で、部屋を案内され風呂は1つしか無いと言われ、団体は銭湯へ入って貰っているそうだ。
「うちの湯はぬるいので」としきりに女将さんが言われたが、何のことは無い適温だった。熱すぎてゆっくり入れないより余ほど良い。
湯舟は超レトロタイル風呂で、鶯宿温泉の廃業した石塚旅館よりも上をいっている。湯縁のタイルの欠けが目立ち、あたると角が痛いくらいだ。
湯縁の紅色のタイルには白く析出物が付着し、色褪せているが新しい壁タイルの紅色ラインとコントラストを描いている。
湯底は薄蒼い丸タイルで、鄙び感が漂う雰囲気はなかなかなものである。
そして何よりの感動が源泉蛇口で、ずっぽり覆った真っ白な析出物は、そのカランをミッキーマウスに仕立てていた。
レトロタイルの湯船と共に、源泉カランで感動する事もあるが、この宿のは銘品と言っていいのではと思う。
温泉は硫酸塩泉とざっくりした成分表示に書かれていたが、ナトリウムもかなり多く含まれているのではないかと思う。湯上りの温まり感が強く、スベスベしたとても気持ちの良い温泉だった。下諏訪温泉の一源泉を引湯し、かけ流しでの提供である。
と言う事で温泉は良かったのだが問題がいくつもあった。
まず1つしか無い風呂は家族用でもあり、夜の9時半ごろから結局は12時頃まで、家族が使用し入れなかった。
朝こそ入ろうと浴室を開けたら、脱衣かごには家族の衣服が脱ぎ棄てられたままであり、不快でしかなかった。
入浴時間を伝えてくれてあればその時間に入るのだが、何も言われなかったので嫌な思いばかりをしてしまった。まるで家の風呂をこっそり借りている様な感じを受け、何と家族中心の宿なんだろうと思った。
他には、浴室前のトイレは家族専用。テレビは付かない。ポットの湯はかなりぬるい。トイレは和式水洗。部屋にこたつはあったが、ファンヒーターを就寝時は必ず消す様にとの注意書きもあった。
これで素泊まり5000円を超えるとは、やはり下諏訪温泉の宿は高いだけでなく、宿中心であったり家族中心であったりするのは、他の宿でもなのだろうか?かろうじて源泉かけ流しの温泉だけは気持ち良かったけれど・・。
131.レトロを求めるとカメムシも付いてきて・・
yottusan様お元気で何よりです!
昭和レトロを求めると、どうしてもカメムシが付いて来ることが多くて参ってしまいます。
山田温泉小谷館そんなに酷かったんですね。微温湯二階堂もですが、昨秋は鶴の湯の本陣棟でも大発生し、皆で食事中に格闘しなければならなかったり、折角取れた本陣の部屋を放棄した方もいらっしゃった様で、会計時「申し訳ありませんでした」とお宿の方が誤まって下さっていましたが、仕方ありませんよねこればかりは。
私なんかレトロタイル風呂を求めるものだから、ある程度の覚悟もしていかなければならないのかも知れませんが・・
瀬見温泉喜至楼では、連泊を取りやめ逃げだしましたね。夜が寝れないというのは流石に我慢できません。
安心なのは外気温が氷点下が続く地域の宿くらいかもしれませんね。
あとはやはり建物に寄るので、まあタイル風呂を持つお宿でも出ない所もあったりで、そういう比較的新しそうな建物の宿はちょっとは安心ですが。
宿だけでなく日帰り施設でも山の中の施設は要注意で、白布温泉森の館は最悪でした。
カメムシも温暖化の影響みたいで何だか年中居るみたいだし、これからの時期はますます覚悟が必要になりますよね・・困ったものです。
130.ご無沙汰してますがお変わりありませんか。
私は鈴木旅館お向えの山静館を利用しました。
仰せの通り登別の喧騒と静かな環境、リーズナブルな価格で
決めましたがカメムシの被害は無かったです。
私のカメムシ経験は昨年四月の小谷温泉山田旅館での
部屋の中は勿論、就寝前の蒲団の中、翌朝の草餅の包みの中
止めは隣接史料館の床での夥しい数でどこを歩けば良いか
躊躇するほどの状況でした。
129.登別・カルルス温泉の昭和を残す宿
yottusann様、カルルス温泉行かれたんですよね?何処のお宿に泊まられたのでしょうか?
タイル風呂を求めて私は鈴木旅館へ。昭和40年代を残す宿で、売店には懐かしい不二家のペコちゃんの飾り物が沢山並んでいました。
お宿に寄付された大漁旗や、パッチワーク等も飾られたりで、昔から馴染みのお客さんがいた事が解る宿でした。
玄関外では居付いた野良猫も6匹以上見かけましたが、何匹だかも解らないくらいの猫が玄関口に餌を貰いに訪れるそうです。
温泉ですが、とても広い浴場には内湯しか有りませんでしたが、浴槽が3つに分かれ、湯量は豊富そう。
3つの浴槽は全て水色の、湯底は丸タイル、槽内は角タイルで造られており、それらを取り囲む様に湯縁は赤茶色のレンガ似たタイル?で造られていました。
また、浴場の床の一部にはレトロタイルも残っていたり、ガラスで造られた壁も昭和を感じさせていました。
カルルス温泉は、登別温泉をスキー場の方に山を登って行くと在るので、白濁硫黄泉かと思いきや、無色透明無味無臭の単純泉で、46℃の源泉をかけ流しており湯船では適温。
刺激が無いので肌が弱い方には良いかも知れませんね。療養泉になっているみたいですし。
個人的にはかなり物足りなかった温泉ですけれど・・。
入浴中にふと気づいたのですが、男女の浴室がすりガラスで仕切られており、そのガラスの近くを通る男性の姿が透かし彫りに見えてしまっているのです。
そのことに気が付かなかった自分は、仕切りの横をウロウロと歩いてしまっていました。
もし、鈴木旅館の温泉に入られる女性の方がいらっしゃったら気を付けて下さいね。
そのためもあってかどうかは判りませんが、宿泊客のほとんどが男性で、私以外に女性といえば、高齢者のご夫婦と後期高齢のご婦人お一人だけでした。
とにかくカメムシが多くてトイレや廊下等、そして部屋には10匹以上出現して・・ガムテープを持って始終格闘しなければなりませんでした。
これらが揃えば残念ながらどうしても女性客は引いてしまうかも知れませんが・・
登別温泉の喧騒から離れて、静かな温泉宿をお探しの方や、リーズナブルな価格での宿泊をご希望の方、カメムシに負けない方、硫黄泉が苦手な方には宜しいかと思います。
128.黒湯に黒タイルの浪岡駅前温泉
青森県浪岡市のJR浪岡駅より徒歩5分程の所にある、名前も浪岡駅前温泉。
余談だが、浪岡駅にある観光案内所も兼ねる広い交流(待合)スペースでは、Wi-Fiも使えるし電源コンセントもありとても便利。
また、青森空港行の路線バスも出ているので、待ち時間にも行ける温泉でもあり、此処でその場所を聞いて向かった。
その大衆浴場は町中という立地のせいだろうか、物凄く賑わっている。次から次へと重複しながら人が入って来る。青森の温泉にしては珍しい。
様子を伺ったが、写真はとてもじゃないが撮る事はできなかった。
黒湯に身を沈めながら洗い場の風景が目に入る。確か下諏訪の共同湯でも見かけたがどうしてこうも洗い場で、皆さん身体を赤くなるまで磨き上げるのだろうか?まるでひと月ぶりに風呂へ来たかの様に、お互い背中をこすり合っている方達が本当に多い。
かと言って、皆さんの肌は色白でもち肌なのだ。これだけ磨き上げるからなのだろうか?と思うくらいに美しいのに・・。
習慣?そうなのだきっと。そう思っておこう。
で、その人気の温泉は黒湯でとても良く温まる感がある。ツルスベで温まりの温泉、これも人気の理由のひとつなのだろう。
モール泉?かと思ったくらい、色が黒く湯底は全く見えず、香りも何だか微かに墨っぽい良い香りも感じられた。
でも後で成分表を見たが、腐食値との文字は一切書かれていなかった。
これで単純泉?というのも摩訶不思議なくらいとても良い湯である。
湯縁はタイル造りなのは判ったが、浴槽内もよおーく見てみるとタイルだった。しかも共に黒色タイルで、湯縁は細かい角タイル、槽内は一般的な角タイル。どちらもレトロタイルであった。黒湯に黒タイルとは粋な感じだ。
茶色のどっしりとしたライオンの口から源泉が投入され、温泉成分のナトリウムに寄るものだろう、湯面に泡が立ち次から次へと流れて行く。これは汚れの泡では無いと判断した。
が、残念な事に余りの人の多さに湯面に垢が‥かなり多くの垢が浮いており、洗面器で汲みだしながら入っているのは私だけでは無かった。
朝一番何て来れる訳は無いけれど、あさイチに入れる人は大変気持ちの良い温泉なのだろう。
127.虎杖浜温泉民宿500マイルにもあったタイル風呂
民宿500マイルは、あの海が見える露天風呂が有名だが、内湯も2つ在り何とその1つが思いがけずレトロタイル風呂だった。
しかもよく見ると、丸タイルがとても可愛くデザインされていたのだった。
浴槽の縁周りに並ぶタイルは、パッと見は、角タイルの絵柄かと思うが近くでよく見ると、白い目地に丸タイルが埋められて模様になっていたのだった。
一つ一つが手作業で。だからよく見ると違いがある。味わい深さが有り、そして可愛くモダンでもある。
浴槽内は紺の丸タイルで造られ、派手さは無くシンプルだが、周りのこのタイル模様が湯舟をオシャレで可愛くさせていた。
引湯された源泉はヌルヌルで上質、非常に気持ち良い露天風呂と共に楽しんで頂きたい湯舟である。
日帰り入浴は貸切2000円で、露天風呂含む3つの湯船が利用できる。
126.虎杖浜温泉ヌルヌル湯のホテル王将
虎杖浜から白老のあたりには100本もの源泉があるという。民家でも温泉付きという贅沢さで別荘にしたり、移住してくる方もそこそこいるらしい。
虎杖浜温泉郷はやや点在しているが(何といっても広い北海道)幾つかの温泉があり、泉質も均一ではなく湯の色も若干違ったりする。
そんな中の一つホテル王将は、虎杖浜温泉に於いて混浴露天風呂を持つ唯一の温泉宿である。
建物は古い。玄関口にある太鼓橋もレトロを強調している。
だからこそレトロタイル風呂が残っているのだ。
広い床の豆タイルが立派で、浴槽は簡素な長方形。タイルの色使いも可愛くも無い男性的な浴槽で、壁に使われているピンクと水色のタイルが逆に不似合いだ。
しかし、浸かった温泉が秀逸だった。ヌルヌル感が凄く、湯の色も少し緑っぽい。
湯縁も床も、温泉成分でかなり茶色くなってしまっている。
ナトリウム泉だろう、かなり温まってくるし、とても良い温泉だと思いながら浸かっていたが、上がって成分表を見て首を傾げた。
総成分が僅かに1,000mgを切れており単純泉となっている。
PHも8.0台だが浴感的には9.0台あるくらいのヌルスベだし、これで単純泉は無いだろうと成分表を睨みつけていた。
内湯の細い出入り口から外へ出ると、直ぐ混浴露天風呂に繋がる。
大きくは無い岩風呂で、眺めも何もない。男女の間仕切りがあるが、湯舟は一つで繋がっているので、カップルでのご利用も多いようだ。
内風呂よりもこの露天風呂を利用する人が多いのか、残念な事に垢が浮いていたので、最後にもう一度内湯に入って洗い流してから上がった。
宿は古くトイレも古いが、良い温泉であった。
125.虎杖浜温泉の美しき湯舟
虎杖浜温泉郷に残っていたレトロタイル風呂、山海荘。
ごめん下さいと何度か声をかけてようやく高齢の女将さんが出てきてくれた。
ご主人を亡くされてからは、日帰り入浴だけは続けてくれており、宿は荒れた感じは無く小ざっぱりとし、今でも宿泊客を迎え入れてくれているかの様に、玄関口にはスリッパが並んでいる。
男女別内湯の他に、家族風呂が3つあり、料金も違う。どちらにしますかと言われ、う~ん・・(どちらも見てみたい)という私の心が見透かされた様で「見てみますか?」と言ってくれたので喜んで見させて貰った。
玄関を入って左側の廊下に家族風呂が3つ並んでおり、湯船の容は皆同じ造りで、床の丸タイルの色が一つだけ紅色で、他は紺色だった。
続いて女性用浴室も、そして男性用浴室まで覗かせて貰った。
こちらは男女とも同じ色のタイルで同じ造りだった。
総タイル造りの四角い湯船が2つ並んでいるが、湯船の一部はカーブを描き、湯縁は重なり合っている珍しいデザインの湯船で、タイルは丸タイルが用いられているが、湯底・湯縁・床とそれぞれ色が違い、段差の部分には長方形のタイルが用いられていた。
どの湯船に入ろうかちょっと迷ったが、やはり最初に見た、陽が差し明るい家族風呂の湯船が印象的で、そこにした。
小さい扇形の湯船だが、湯縁が彫刻されている様に見え、それは小さくともとても重厚なタイル風呂に思えたのだった。
しかし間近で見るとその湯縁は、黒い豆タイルの上に白く析出物が固着したものが並んでいるのだったが、シアンブルーのタイルが更に湯舟を神秘的な物に見せていた。
床には青い丸タイルが敷き詰められており、丸く穴を開けた部分が排水溝となっていた。同じく天井に丸い穴を開けパイプを入れた物が湯気抜きである。
温泉は無色透明無味無臭の単純泉で、味気なかったが、総レトロタイルの湯船は宝石入れの小箱の様にも見えた。
造られてから50年近くになるようで、昭和40年代はモザイクタイルが一番多く用いられた時期でもあったのだろう。
これが50年代のタイル風呂となれば、タイルが新しく綺麗な物が多く、60年代にはレトロタイルは姿を消し、代わって表面が滑り止めを果たすザラツキを感じる新タイルとなっている。
やはり総レトロタイルの湯船は貴重である。
家族風呂は1時間で400円。男女別湯舟は300円。
124.栃尾又温泉のタイル風呂
栃尾又温泉と言えば、下の湯・奥の湯・上の湯の3つの浴場の温泉を言い、源泉は一つのラジウム源泉である。
源泉に一番近く地下にある下の湯と、一階に造られた奥の湯は岩風呂であり、浴槽の中はタイル造りではあるが、10年程前にリフォームされた新しいタイルであり、レトロタイル風呂に近い浴槽を持つのは上の湯である。
上の湯の浴槽内の紺~藍の丸タイルは、新潟の清廣館や川内高城温泉の竹屋旅館、飯坂温泉のつたや旅館と同じ物であったが、浴槽自体は紺色の10㎝程の角タイルで造られ、投入口も同様のタイルで造られており新しさを感じる。
源泉槽・寝湯・加温槽の3つの湯船が連なり、いずれもが同じタイルを用いた造りの湯船だった。
上の湯は、下の湯・奥の湯とは雰囲気が異なる浴場であり、これら3つの浴場の中ではこの上の湯の湯船が一番古く、30年程前のものだそうだが、となると昭和60年頃のタイル風呂という事であり、この年代にまだこの様なタイル風呂が造られていたのだなあと‥
レトロな丸タイルが用いられていたが、タイル風呂としては最後の方の時期に造られた湯舟ではないだろうか?
123.糠平温泉花型のお風呂
北海道、糠平温泉郷のレトロタイル風呂を持つ中村屋。こちらのお宿のお風呂は大きな花型をしていました。
訪れたのが夕方で浴場内が暗いのが残念だったのですが、明るい時間帯に入るとガラスブロック壁からの光で、断然明るくもっともっと可愛い湯船だったのではと思います。
昭和30年代に造られたそうですが、大浴場の大きな花型タイル風呂は、もっと新しいのではと思えるくらい綺麗なままで残っており、お宿の自慢の浴場との事でした。木風呂との男女日替わりです。
糠平温泉郷は源泉かけ流しをうたっているのですが、貯水槽から各宿への引湯であり、そのためもあってかほとんど湯の特徴を感じない温泉でした。表示を見るとギリギリ単純泉を脱したナトリウム‐塩化物・炭酸水素塩泉でしたけれど。
中村屋は他に混浴露天風呂があり、カップルに非常に人気で、個人的には女性専用時間帯まで入る事はできませんでしたが、夜に電気を消して入る露天風呂からは、満点の星空が眺められとても美しかったです。
館内も素敵な雰囲気でお料理も良かったので、糠平温泉郷に於いてトータル的に人気の温泉宿の様です。
冬の糠平湖ではワカサギ釣りのテントが立ち並び、アイスバブルやきのこ氷を見に行くツアーや、タウシュビツ橋梁ツアー(年間通して)が行われており、北海道でしか見られない風景が此処では見られ、冬の北海道の良さをとても感じられました。
122.飯坂温泉タイル風呂巡り⑤喜久屋旅館
飯坂温泉には共同湯がいくつもあり、建て替えられた有名な鯖湖湯や波来湯を始めとし、古くからのままの大門の湯や八幡の湯などでは、湯船もレトロタイル風呂のまま残っているか訪れてみたが、天王寺穴原湯の様なタイル造りの浴槽は見られなかった。
どちらかと言うと、共同湯よりお宿の方にはレトロタイル風呂がまだ多く残されており、喜久屋旅館の女性湯がタイル風呂であったので訪れてみた。
花型の半分と言えば良いのだろうか。花びら型の浴槽は、花びら部分は石であったが、湯船の中はブルーの角タイルで埋まっていた。
投入口は温泉成分で黒と黄色と白の縦縞模様になり、フグの様にトゲトゲが覆い、受け皿に乗せられた小石は牡蠣殻の様に見えるくらいゴツゴツしていた。
ただ、湯は熱めの無味無臭の単純泉で、浴感も何も印象に残る様なものは感じられないのが残念でもあった。
源泉が50℃~60℃ある飯坂温泉だがそのほとんどが単純泉である。
鯖湖湯では多くの人が訪れ45℃くらいの湯船に真っ赤になり浸かっている方が多く、私も辛抱して浸かってみたが、ただジンジンと熱いだけで、温泉津温泉の様なキューっと身体に沁みいる様な気持ち良さは全く感じられず、我慢していても仕方ないのでサッと上がってしまった。
温泉津温泉との泉質の違いは大きく、癖になる気持ち良さを持つ温泉津に比べ、ただ熱いだけの飯坂温泉では、我慢しても浸かる意味が無く物足りなかった。
そんな中で、場所を移転したという天王寺穴原湯は、もしかしたら湯舟はそのままで移築したのかも知れずレトロタイル風呂を持ち、しかも硫黄の香りも持ちながら、熱いけれど気持ちの良い温泉であるので、飯坂温泉へ訪れた際にはぜひ足を運んでみて頂きたい共同湯である。
冬にも平野屋旅館を選んで宿泊したが、平野屋の温泉はぬるめである。
「ゆっくり長く浸かって下さい」と予めご主人からも言われ、心して浸かる。
そして思った。42℃は確かにとても気持ちが良いがそう長くは浸かっておられい。ならば40℃程のぬるめの源泉にじっくりゆっくり浸かるというのは、大変気持ち良いものではないかと今更ながら。
121.飯坂温泉タイル風呂巡り④一柳閣と栄楽
飯坂温泉郷へ訪れ初めて入った温泉が一柳閣だった。床、湯縁、湯船と完全なレトロタイルのまま残った浴槽には、透明な飯坂温泉の熱い源泉が僅かずつ掛け流されており、ほのかに硫黄臭も感じるとても気持ち良いものだった。長年の温泉成分で投入口付近は黒くなり、タイルが揺らめいていた。
この熱い温泉とその気持ち良さが飯坂温泉の第一印象となり、この温泉を基準としてこの後数件の飯坂温泉を巡る事となったが、結果的に硫黄臭を感じたのはこの一柳閣と、ここよりも強く感じた天王寺穴原温泉共同湯の2軒だけだったように思う。
温泉自体の気持ち良さも、1番は天王寺穴原温泉共同湯で、2番目がこの一柳閣の様に思う。
一柳閣も熱い源泉だったが入った時には加水せず浸かれ、それで気持ちも良かったのだが、もしかすると私が入浴する前に、近くの老人施設のお年寄りの方たちが入られ、既に加水された温泉であったから浸かれたのかも知れなかった。
日帰り入浴を問うた時、女将さんが「しばらくおばあちゃんたちは入らないと思うから」と言われたので気が付いたのだが、お風呂へ入り食事もしお昼寝タイムであった様だ。
そう言えば近くに老人デイサービスがあった。皆さんで時々温泉へ入りに来ている様なのだな。最高の楽しみなのじゃないだろうか。
もう一つ、栄楽という温泉宿がレトロタイルを用いた湯舟を持っていたが、湯縁は黒石。
料理宿と銘打っているのは、昼はカフェを営んでおり、ランチや仕出しもある料理自慢の宿であるかららしい。
だが、食事をすれば温泉は無料という訳ではなく、別料金500円が必要。
浴室は家庭的なこじんまりとしたもので、半サウナ状態。籠って熱くてゆっくり入ってはいられなかった。
画像1.2一柳閣 3.栄楽
120.飯坂温泉タイル風呂巡り③鯖湖湯近くのほりえや旅館
飯坂温泉メインの共同浴場鯖湖湯のすぐ近くにあり、屋根の一部の構えもよく似ているほりえや旅館。
その玄関口をくぐり中へ入るとまず目に付くのが、アニメの女の子のキャラクターの丸バッジがずらっと壁一面に貼られており、他に人形なども置かれているのか売られているのか解りませんがというか、興味ないのでよく見ませんでしたが、この宿はもしかしてアニメの聖地?なのでしょうか?
この宿は積極的に日帰り入浴も受け入れてくれており、女将さんが浴室まで案内して下さり、浴室は大・小2つあるけれど男女別という訳ではなく、空いている方、好みの方に貸切で入って下さいとの事でした。折角ですから大きい方へと言って頂いたので、小さい方もちょっと覗かせて頂きサッとカメラに収め、写真によく出ている方の浴室を使わせて貰いました。
湯船の中だけが単一水色のタイルで、縁は黒御影石に替わっているので、建物程のレトロ感はありません。湯舟の中に丸い座石が置かれています。
鯖湖湯に近いためか非常に熱いと言われているようですが、穴原湯に入って来た私にとっては、そこまでは熱いと思えず浸かりました。
大きい方と言っても差ほどの大きさでも無いので、これはやはり貸切風呂・家族風呂といった浴室ですよね。湯気が籠って半サウナ状態でもありました。
夏はいったいどうなることでしょうか・・
此処にも湯舟の縁には年代を経た石造りの蛙の置物が。何軒かで見かけた蛙・・何か飯坂温泉でのいわれがあるのか問うて見たかったのですが、聞かずじまいでした。
ご存じの方教えて下さいませ。
119.飯坂温泉タイル風呂巡り②おかめとひょっとこタイル
一目見てびっくりしたのが、大きなタイル風呂の湯底にこれまたタイルで、女性風呂にはひょっとこが、とすると男性風呂にはきっとおかめが、描かれている事だろう福住旅館。
どなたかのアイデアであるのだろうが、ここにしか無いタイル風呂と言え、記憶に残る事は間違いない。
加水循環されているため湯温は適温で入りやすい。そのためか「ここの風呂が好き」と言われる常連さんと一緒になった。湯舟はかなり大きく快適である。
人それぞれの好みが得られる位に、多くの温泉旅館を持つ飯坂温泉郷。
一体何軒の宿があるのだろう?歩いて回られない訳でも無いが、全範囲の宿となるとかなりの広範囲である。廃業や休業中の宿も無い訳ではないが、車も多く通り、町全体の侘しさというものは無くそこそこに栄えている様だ。
こういった温泉郷の中に、昔からのタイル風呂を持つ温泉施設が、まだ多く残っていたのだった。
透明な温泉であるからこそ、色や柄が映えるタイル風呂が用いられてきたのだろうし、中でも珍しい福住旅館のおかめ・ひょっとこ風呂は貴重である。
おかめを撮りたくて何度か男風呂に足を運んだが、夕方でもあり入浴客がいらっしゃって無理だった。
118.飯坂温泉タイル風呂巡り①つたや旅館
飯坂温泉は湯が透明な事もあり、幾つものタイル風呂が残っている。
その中からまずどうしても入りたかったのが、つたや旅館の目も覚める様な鮮やかな碧タイルが美しい円形風呂。
縁が白い大理石であるため、湯船の中の碧タイルを引き立たせており、しかも円形であるという造りが可愛くもあり、少ないため印象に残る。
ただし、この風呂は男性用で入れ替え無し。
と、ここで諦められなかったのでご主人と交渉に入る。「明日のチェックアウト前の9時半頃、もしどなたも男性が入浴されて居なかったら、男性用の風呂を使わせてもらえますか?」と。
了承を貰えたので、本日は女性用の浴室へ、こちらもタイル湯船だった。
新潟の清廣館と同じく藍色に近い碧い丸タイルがずらっと並び、縁は赤茶色の大きなタイル?だった。
つたや旅館は源泉からの引湯距離が長いが、それでも熱い飯坂温泉を源泉かけ流しで提供するため、湯口までは長いアプローチをとり、少しでも冷ましてから源泉投入できる様に配慮されていた。
そのためか温泉は適温で浸かれ、ツルツルタイルの浴感と清潔感ある湯舟。
そして、この宿は非常にご主人の接客が丁寧で感じ良く、泊まる価値ある温泉宿だと感じた。
翌朝約束通りの時間に伺い、再び入浴料を支払い今度は男性浴室へ。10時には日帰り客が訪れる可能性があるのでゆっくりはしていられない。
広めのガランとした感じの浴室には、碧い円形タイル風呂が静かに待っていてくれた。
窓も縦長に大きく取られており、明るい浴室である。
こちらの投入口は、縁と同じく大理石の丸い容の物が中央にあり、そこから源泉が少しずつ溢れ出ていた。
タイルの色は女性用の湯船より鮮やかな色合いで、この美しい浴場なら女性も入りたいだろうなと思う。
出来れば男女入れ替え制にして貰えれば、もっと宿泊客も増えるのでは?何て。
117.湯もタイルもグッドな飯坂温泉の天王寺穴原湯
西園寺様に教えて頂いていた、福島・飯坂温泉奥にある穴原温泉富士屋旅館へ行きたかったのですが、休業中との事で飯坂温泉共同湯の一つ、天王寺穴原湯という所に行ってみました。
駐車場には結構車が止まっていて割合人気の様子です。
入ってみるとやはり、女性風呂でも3人の方がいらっしゃり、1人が浸かりお二人が浴槽の横で身体を洗ってらっしゃいました。
長方形の湯船はそれ程は大きくなく、ゆったりなら3人程浸かれるくらいで、空いたら浸かったり、誰かが浸かりに来たら上がったりと、それとなく気を利かしながら利用します。
加水用の蛇口もありましたが、私が浸かった時には熱かったですが、加水せずどうにか浸かって居られる程度で、ちょっと我慢して湯舟に身を沈めると、う~ん何とも気持ちいい!
人気の程が解る温泉です。熱いけどとにかく気持ちがいいんです。
堂々とした白ライオンの投入口には、白ゴマ髭が口の周りや顔に析出物で形成されており、大きくあいた口からは源泉が結構ドバドバ投入ですので、湯舟内の湯に流れがあり勿論溢れ出しもあるので、湯垢が浮いているという事も気になら無かったと思います。
そしてそのタイル。湯舟を造っているレトロ角タイルの一つ一つに、経年劣化のヒビが入っており、まるで石に見られる様な多彩なヒビ模様が出来上がっていました。
中には更にそれらのタイルの一部が茶色に変色していたりで、これらはまさか最初からの模様では無いよなと、マジマジ湯船の中まで見つめてしまいました。
色は地味だけれど、湯吞み茶碗などでも見かける様なひび割れ模様を、半身浴で飽きることなく見つめ、もっと見ていたかったのですが、いかんせん熱くて上がりました。
何年前にできた風呂であるのかを尋ねましたが、はっきりとは解らず40年以上は経ってるよとの事でした。
しかし、お湯は気持ちいいし、タイル風呂は味があるしで、実に印象に残る共同湯でした。
この後飯坂温泉の旅館の温泉に幾つも入ったのですが、どうもこの穴原温泉の熱さ気持ち良さが忘れられずでした。
116.ペンギンが立つタイル風呂
小野川温泉二階堂は、うめや旅館の並びにあった。雰囲気のあるレトロ風な建物で、宿泊も日帰り入浴も行ってくれていた。
この宿の一般浴室は、丸タイルを使った縦割り瓢箪型の湯船で、小野川温泉の透明な湯が投入されていたが、循環風呂だった。
この宿にはペンギンが居る風呂が在ると言う事で、家族風呂へ。
おー居た!正方形のタイル風呂の縁の真ん中にペンギンが立っていた。温泉投入口では無く、投入は横のパイプからだったが、何故ペンギン?と問いたくなる。
ブルー系タイルが用いられた可愛い感じの湯船だ。
もう一つ家族風呂があり、こちらのドアを開けると、ピンク系タイルで造られた同じ形の風呂があり、よく見るとペンギンが一回り小さいようだった。
こんな家族風呂なら子供も喜んで入るのかも知れないが、湯船の縁にペンギンが立っているのは初めてだった。
タイル風呂は一つ一つが皆違い、それぞれの個性を持つのが実に面白く、貴重な存在である。
115.宿中心の宿
下諏訪温泉はレトロタイル風呂が残されている温泉郷でもあり、共同湯だけで無くお宿も古くからのタイル風呂をそのまま使われているお宿が幾つかあり、今回はその中の一つ「三代目おくむら」という旅館へ宿泊してみた。
チェックインは16時からとなっていたのだが早く到着してしまい、館内にだけでも入れて貰えないかと思い宿へ着いたのが15時20分頃だった。
しかし、玄関口には鍵がかかり、カーテンまでもが閉められている。
えっ!?もしかして休業?予約が通っていなかった?
見ると扉には紙が貼られており、16時からのチェックインだと書き示されていた。
まあそうだけど・・いや、ここまでする宿は初めてだったので、驚きとショックに見舞われながら雪の積もる外で30分程時間を潰し、5分前に行ってみると玄関のカーテンと鍵は開けられ電気が付いていた。
恐る恐る宿へ足を踏み入れ、不愛想な女将さんに案内されて二階へ。
女将さんは私よりお若く、60代半ばの私はキャリーケースとバッグをどっこらしょっと持ち上げ、女将さんの後を付いて階段を上がる。
階段を数段上がり、女将さんはチラと私を振り返ったけれど「おかばん持ちましょうか?」等の声掛けは一切無く、私が付いて上がって来る事を確かめただけらしかった。
かなり徹底している様だ。一切持たない事に。手助けはしない事に。
その後入浴時間の説明も受け、夜は何時迄で、朝は9時迄と言われた。
宿泊価格が高いので素泊まりにしたので、朝はゆっくり寝て8時過ぎから風呂へ向かった。1時間近く入浴できる時間があると思い。
すると8時半頃には隣の男性浴室から掃除の音が・・
え?もう?9時に浴室を出れば良いのでしょうが、これではうるさくて折角の朝風呂にゆっくり浸かっても居られない。
日帰り入浴は行っていない宿でもあるのに、入浴中にそんなに早くから掃除されては、宿泊してもゆっくりと温泉を楽しむこともできない。
下諏訪の温泉は源泉温度が高く、そのため冬に訪れ熱めの温泉に浸かろうと思って来たのだったが、この宿の温泉は体感的に41~42℃程で決して熱くは無く、どころかもう少し投入量を増やして熱めにして頂いてもと思う位の湯温だった。
組合源泉旦過の湯を引湯しかけ流しにはしているのだが、余りにも投入量が少ないのがちょっと残念だった。
無味無臭の透明の湯が白い角タイルで造られた湯舟に張られ、湯底の豆タイルを映し綺麗だ。
浴室の床は茶系の豆タイルだが、壁は茶系のタイルシートだと思われる。
男女別浴室の造りは同じだが、女性用湯舟は男性用の半分位の大きさで、2人入ればいっぱいという大きさだった。
他に女性の宿泊客はおらず貸切の様にして、熱すぎない湯に浸かれたのは気持ちが良かったが、朝風呂での追い出され感にはがっかりしてしまった。
部屋は和洋室だがトイレ洗面所共用、これで素泊まり1万円近いお値段の宿である。
上記に述べた3点から感じた事は「何とお宿中心の宿なんだろう」と言う事だった。
諏訪は観光客が多いため、総じて宿代が高い所ではある。しかし、共同湯巡りも楽しめる温泉地でもあるので、もう少し庶民的なと言うか、気軽に宿泊して共同湯巡りを楽しめる様な、そんな温泉地であっても良いのではと思ってしまった。
タイル風呂を持ちお手頃価格のお宿を他に見つけたので、今度泊まるときはそちらの宿にしたい。
菅野温泉との間に、とても美味しいお惣菜屋さん兼お弁当屋さんがあるので、
素泊まりされる場合やお昼ご飯に、利用されてみられては如何でしょうか。
114.湯田中・まるか旅館のタイル風呂に惹きつけられて
TAMAISM様の写真に惹きつけられて会いに行った、湯田中温泉に在る、まるか旅館のレトロタイル風呂。あの蛸壺?の様な特徴ある投入口に蒼い湯。
それが頭に残りどうしても行ってみたい、熱い湯と石畳の冬が似合う湯田中温泉へと、青春18きっぷで長野へ。
浴室は貸切で使用するとの説明を受け、部屋に荷物を置いた後、渋温泉へ向かう前に早速ちょっと風呂を覗いてみた。
おぉ・・!TAMAIZUMU様のブログ通り、どころか全くそのままの温泉がそこに在った。
神秘的に美しい透き通った寂び感ある蒼い湯。
何とその溢れ出し、床を濡らし流れる様までが美しい。
そしてシックなレトロタイル風呂の端には、これまた写真通りの、赤茶けたレンガ色の割れた壺の様な投入口が。
いやあ素敵・・もうこれは入らずにおられない。まずこの温泉に浸かる事にした。
湯田中の湯は熱い。確かに酷く熱かった。源泉かけ流しの湯を、何杯かかぶり湯をしてそっと湯舟に身を沈めて行くが、身体は赤くなる。が浸かる。
湯が蒼く見えるのは湯底のタイルがブルーのせいだが、タイルのツルツルとした触感が心地良い。
この冬に窓は全開。こうして温泉を冷めさせているため、まるで露天風呂に入って居る様に、身体は熱いが顔と頭は冷たいといった、現象になっている。
う~ん・・いい。貸切風呂で入れるのが良い。泉質は差ほどどういう程の物でも無いが、この湯舟自体が持つ雰囲気は他には無い。
そして、内湯でありながら露天風呂に入って居る様な感覚で、一人きりで静かに秘かに浸かっているのが実に良い。
後で女将さんに問うと、どうやらあの投入口は昔使われていた物の様で、今は使えなくなりパイプから源泉を流しているとの事だが、夏は熱過ぎて入れないと言われていた。
パイプを筒ではなく半割にして源泉を冷ますとか、もっとルートを長くして冷ますとか、何か別の物にしたらもう少し源泉も冷めるだろうにと思ったが言わなかった。
朝起きると景色は一変。真っ白な雪で辺りは覆われていた。起床時の熱めの温泉が楽しみである。
おそらく一晩中全開であったのだろう。冷えた浴室のその窓からは、雪を被った庭木が見え、熱い温泉が早朝の身体に沁みわたる。
湯の蒼さは光の加減か、朝はそれ程では無かったが、窓から見る雪が良い。
・・・ふ~む。
そうか、内湯でありながら半露天風呂の様なロケーションを持つ浴室と、熱い源泉が流れるこの雰囲気ある湯舟は、一体化しているのだな。
こうして長い間此処に佇んで来ていたのだ。これからもずっと。
何と言うか、風呂が物で無い様な・・何だかそんな感じを受ける、何とも独特な不思議な個性を持つ、まるか旅館の温泉であった。
113.2食付きで実質300円だった飯坂温泉の宿
全国旅行支援を利用し「料理付き日本で一番安い宿」と銘打っている飯坂温泉平野屋旅館へ。
予約時の電話対応も良く「お待ちしています」と声も掛けてくれる。
明治時代からの温泉宿は、今のご主人で4代目だとか。館内はかなり古びており「あ、そこ危ないですよ」と言われた廊下の一部は、へこんでいてつまずきそうになった。
赤カーペットだっただろう物は黒ずんでいる方が多く年季を感じ、2階の廊下には今まで見た事も無いくらいトンデモなく大きい年代物の鏡が。
しかし案内された部屋は広く、既に布団が敷かれ、テーブルには茶菓子も。
部屋はトイレ・洗面所付きで、トイレは男女共用の水洗和式型だが、冬には温め機能も無い洋式トイレよりはいいかも知れない。
お茶セットの他には、テレビ、電話、冷蔵庫、エアコン、そして驚いたのがガスストーブが点けられていた事。
格安宿となると石油ファンヒーターが圧倒的に多く,アレは匂いも臭く3時間毎で切れてしまうので実に不便なのだが、この宿は有り難い事にガスストーブだった。しかも暖房費取らずで。
安いだけで泊まった訳ではなく、浴槽がレトロタイルだったからであったが、写真で見ていたタイル風呂は男性浴室だけであり、女性浴室の壁等にはレトロタイルが残っているが、浴槽は造り替えたのだろう石造りだった。
男性浴槽の中は昔からのタイル風呂で造られており、かなり大きい。というか女性の風呂がかなり小さい。
大きさの男女差が激しいが、この宿の泊り客の多くは男性の様で、ビジネス利用やバイクツーリング客等が多いらしい。
浴衣もタバコ臭かった。加齢臭よりはマシだけど。クリーニングに出してはいる様だが、染みついたタバコの臭いは取れないようだ。
話を温泉に戻すが「うちの風呂はぬるいですよ」とご主人に言われたが、熱い飯坂温泉にあってぬるかった。体感的には39℃から40℃くらいにぬるい。
飯坂温泉の源泉は数か所あるそうで、ほとんどのお宿はその源泉のどれだかを引湯しており、平野屋さんは「100メートル程引湯してきている」との事で、その間にかなり冷め、香りも飛んでしまうのだろうけれど、おまけに投入量も少ないので女性風呂はぬるかったし、無味無臭の単純泉だった。湯温的には秋とか春とかが丁度良いかも知れない。
さてこの宿に有って驚いたのが食事。評判も悪くなくボリュームもあるとの事だったが、朝・夕共に部屋食で、大きなお盆2つに載せて運ばれてきた、その品数と量の多さにびっくり。
とにかく何でも多いのだ。天ぷらに付いたカレー塩の量は通常の10倍程もあり、漬物も山盛りされている。そして一番驚いたのがおひつに入ったご飯。ぎゅーっと白米が詰め込まれ茶碗7、8杯はあるのじゃないかと思う位多い。
「食べきれないと思いますが」と言って出されたお料理は美味しく、魚は新鮮で臭みが無く、いつもは残す冷凍鱈も生鮮で美味しかったので食べたし、最後のリンゴまで口にした時には満腹過ぎる程満福になった。
食事を下げに来てくれたご主人に「何か代々言い伝えがあるとか?ボランティア精神でとか?
とにかくお客さんに喜んで貰うためにとか?」と唐突に不躾な質問を投げかけてしまったら、へッ?とした顔をされて「何もありません」と言われた。
「明日の朝食をお持ちする時にお会計を」と言われ朝食がお盆に入れて運ばれて来た。朝から炊き立ての白いご飯が、おひつに詰められている。
「3300円になります」とご主人。「実質300円ですよね」と私。「そうなりますね」とご主人。
・・驚愕過ぎて顔も笑えない。確かに実質0円の素泊まり格安ホテルも利用して福島まで来ているが、この料理が付いて一人泊300円とは・・
今まで泊まった料理付き宿の中で一番安かったのは、帯広のホテルボストンで、でもあそこは素泊まり価格は普通で、料理が安く朝夕で1500円。合わせて5000円前後(部屋の違いによる)になるのかな。
平野屋さんはスタンダード5500円で、ビジネス食で5000円だそうだが、ビジネス食でもかなりボリュームがあり、男性でも十分に満足するらしい。
おまけにあのクオリティの高い部屋環境は、一般の旅館と変わらないかむしろ上をいっている部分もある。そして何よりも凄いあの料理。あれで一人泊2食付きの価格とは破格である。
私が今まで泊まった中での、コスパ抜群お薦め料理宿ベスト3のひとつにランクインした。
後の2軒はレトロタイル風呂の中で紹介させて頂いている、板留温泉民宿佐々木と鶯宿温泉鴬泉館の2つ。
全国旅行支援を利用して高くて行きにくかった宿に行く事もするが、こうして格安宿に更に格安に泊まるのも好きだ。来年も1月10日から、割引率は下がるが再スタートするそうなので、冬の寒い時期に熱い飯坂温泉へ是非どうぞ。平野屋旅館の前には共同湯の波来湯も在りますよ。
112.会津東山温泉のかなり鄙び宿
会津東山温泉は大旅館が多いが、その中に2軒レトロで鄙びた温泉宿がる。
1軒は以前紹介させて貰った東山ハイマートホテル。そして今回見つけたのが更に鄙びた二洸館。
東山温泉にもこんな宿が残っていたのかと思う位の鄙びた感満載の建物。
改装中なのか?被災によるものなのか?青いビニールシートがかかったままの建物・・。
日帰り入浴の確認電話を入れると、不定休の様であり、不確実な返事であったため、二度確認の電話を入れてから訪れた。
館内は予想通りの雑多さ。営業しているのかどうかもよく解らない感が漂う。
これで某旅行サイトでは、全国旅行支援にのっかり桁外れな2食付き15,000円という、ぼったくりもいい価格で掲載していたのには呆れる。良かった他の宿にして・・と、ほっとする。
土曜日、誰も宿泊していないだろうと思ったが、1人入浴後の男性が現れた。泊まりなのか日帰りなのかよく解らない感じだったけれど。
レトロタイルの浴槽は、男性浴室と女性浴室では容も違い、女性浴槽の方が大きめで浅い部分もあったので、もしかしたら母親が子供と一緒に入るために造られているのかな?と思った。
昔からそのままのタイルは所々が剥げていたが、まずまずの美しさで保たれ、
温泉は湯底注入の組合源泉。ナトリウム・カルシウム・硫酸塩泉で、泉質にナトリウムが入ると浴感が柔らかく良く温まる。
女性浴室の入り口にはタイルで造られたレトロな洗面台も、当時のままの姿で残されていた。
う~ん・・いつまで温泉宿として営業を続けるのか、このタイル風呂へ入る事ができるのかは、ちょっと疑問な不思議感ある温泉宿であった。
111.下諏訪共同湯のレトロ風呂
下諏訪共同浴場の中で現存している共同湯は8湯あり、その中でも残されているレトロな温泉を探して、3つ入って来ました。みなみ温泉もレトロだったのですが2019年に閉業してしまっています。
①矢木温泉:看板からしてレトロ感があり、浴室床や周囲には四角く淡いピンクのレトロタイルが敷き詰められ、浴槽の中は色違いの薄青いタイルでした。
湯縁が石に替わってしまっているのが残念です。
目立つのは碧いタイル壁画。荒れた波の上を一羽の黒鳥が飛んでいます。
真ん中に立てられた湯温計は、温泉津温泉と同じタイプでレトロ仕様。
熱いけど気持ち良い温泉でした。
②新湯:半楕円形の様な変形造りの浴槽は、レトロタイルとまでは言えない大きめのタイル造りですが、存在感があるのがライオンの投入口で、析出物の付着もあって貫禄ある白ライオンとなっています。
タイル壁画は富士山でした。小ざっぱりした造りの浴室です。
③菅野温泉:西園寺様の投稿に写真を載せて下さっています。
下諏訪共同湯を代表するレトロ感溢れる共同湯で、外の通路や番台や、まだ置かれている昔のパーマネント風ドライヤー?等懐かしさ一杯です。
大きな楕円形の浴槽は、とっても可愛いレトロタイルで、湯底の花柄デザインのブルータイルは唯一無二?かと思ったくらい、初めて見たものでしたし、縁の紅タイルとマッチして、どうしても写真に収めたいくらい可愛く綺麗な浴槽だったのですが、撮らせて貰えませんでした~。
下諏訪温泉は源泉温度98℃の塩化物泉なので、何といっても冬がいいですよね~。
他にも1日休憩室付きの共同湯や、諏訪湖近くにある大正ロマンの片倉館など、1日使って温泉巡りを楽しめる処でもあります。
お宿にもレトロタイルの浴槽を持つお宿が残っているので、今度訪れてみたいと思っています。
110.神秘的な蒼のタイルに揺れ煌めく温泉
岩手・金田一温泉郷にあるおぼない旅館。「おぼない」とはどういう意味なのか問うと「小保内」という苗字との事であった。料理旅館であり、広い食堂には洋食皿が並べられ、夕食の用意が進んでいた。
ちなみにこの宿は、庭に素敵なキャンプ場も持っており、コロナ禍では旅館泊だけでは無く、こういった形態もある温泉宿は人気であるだろうなと思った。
さてその温泉だが、どなたかのブログ写真で美しい湯船の写真を見て、おぼない旅館を知った。その美しさに一目惚れし、旅の予定を変更して訪れた温泉だった。
やや暗めの広い浴室の端に、重厚感ある浴槽があり、湯は蒼く煌めいていた。
湯縁はコンクリート造りで、大きめの小石がバラバラと埋め込まれており、温泉成分に寄りすっかり赤茶色に変色していた。
L字型に造られた湯舟の側面には、ターコイズブルー~シアンブルーのレトロタイルが用いられており、その一部は温泉成分により黒茶色に変色し、経年を感じる渋さがある。湯底は豆タイル。
単純弱アルカリ泉の透明な温泉は、これらのカラーに取り囲まれ、蒼く神秘的で鉱質的な煌めきを放っていた。
温泉の一部に僅かに陽が入ると、尚更蒼いタイルに映え輝く。
その美しさを撮りたいと、湯船の中を歩き回ったり外へと、出入りを繰り返したが、残念な事にスマホでは上手く撮れていなかった。
浴室のタイル壁画は洗い場でも見られ、一部にはガラスブロックも用いられているレトロモダンな温泉浴場であった。
温泉はドバドバ投入されており湯面が波打つが、加温循環泉。塩素臭は無かったが、これが源泉かけ流しであれば、どれ程素敵だろうかと思う。
もしくは、33度の源泉冷泉風呂も備わっていればと思うが、寒い地方の方々はぬる湯や冷泉はお嫌いなようで、どの宿も加温泉のみである。
日帰り入浴は10時~18時で料金600円。
109.男女合わせて巨大ひょうたん風呂だった
座敷童で有名な岩手の金田一温泉。数件ある宿の中でも、タイル風呂を持つ仙養館に宿泊してみた。
この地方でありながら宿泊価格が何故か高いなあと思っていたら、加温源泉だった為であった。
源泉温度33度の単純弱アルカリ泉を加温循環させているのだが、仙養館の湯船には何故か水道のビニールホースが。ここから温泉を出していると言う。
女将さんいわく「循環するとレジオネラ感染を起こすから」との事であったが、レジオネラ感染を一度起こしたので循環を止めたのか、起こすことを予防してホースに替えたのか、そこは強く聞けなかった。
なのに湯舟に浸かると、他館ではしなかった塩素臭が、何故か此処では微かにする??
循環泉では無いのに何故?清掃に使われている?かとも思ったがそうでも無い様である。
金田一温泉郷の宿は自家源泉ではなく、数本ある組合源泉をそれぞれ近くの宿が引湯しているそうだ。
引湯した源泉を一度タンクに溜め、加温してからホースで流している仙養館では、おそらくタンクの中に塩素を投入しているのではないかと思われる。
実は、湯船には立派な投入口(赤いタイル造りの大きな円形物)が付いており、それを使用していた時は循環であったのだろうけれど、今やそれは空しく使われておらず、ビニールホースからの温泉投入となっている。
民宿でホースから源泉が出ていた宿はあったが、旅館でホースというのもどうかと思うが・・。
円形のタイル風呂かと思われた湯舟は大きくて、女性用の浴槽でも10人は浸かれるものだった。
しかしよくよく見ると、壁で仕切られた向こうは男性用の浴槽と繋がっており、これが1つのひょうたん風呂である事が判明した。
男女浴室の仕切り壁には、とても珍しいカラーガラス板が用いられていて、ひょうたん型の浴槽を上下2つに分けている。
瓢箪の上部の女性用湯舟でもこんなに大きいのだから、男性浴室の湯船はどんなに大きいのだろうと興味が湧いて、女将さんにお願いしてちょっと覗かせて貰った。
大きい!これ程大きなひょうたん風呂には初めてお目にかかった。これが一つの瓢箪となると、とても巨大なひょうたん風呂だ。そしてそれを収めていた浴場は大変な広さでもある。
「昔は混浴だったんだけど」と女将さんが言われる。確かにこの様な大きなひょうたん風呂を造っておれば、当時としては当然だろうし、おおらかな在りし日がちょっと浮かんだ。
ph7.9の温泉は、循環していないぶん他館よりややヌルヌル感が強いように感じた。
他館の透明な温泉に比べると、此処のは何故か僅かに白っぽく濁っているので、女将さんに尋ねたら「たまにドッと湯の花が固まって出るから」と言う事であった。
浴槽の湯縁はおそらく黒のレトロタイルだと思われるが、析出物で白っぽくなってしまっていたが、側面や湯底はブルー系の豆タイルで造られ、欠けや剥がれは無くしっかりした造りである。
宿はまだ40年程前のものであるそうなので、浴室や湯舟もそう古いものでは無いが、ガランと広い浴室の壁には茶系や黒のタイルが用いられ、錆びついた窓枠のガラス窓から見える緑と、青いビニールホースが侘しく、寂び感が漂うレトロ温泉であった。
加温源泉を出しながら浸かり、上がるときは勿体ないので止めておいたが、そのままでも良いそうである。どうしたものか迷ってしまう。
ラジウムも含有している温泉をしっかり加温されているため、非常に良く温まり浴後は汗が出て暑くてたまらなかった。
個人的には、夏は源泉33℃の冷泉のままで入りたい!交互浴がしたい!と希望したが、管理上それはできないそうだ。残念である。
座敷童が出るどころか、カメムシが出る年季のいった宿で、女性客は1人であったが、土曜の素泊まり泊8704円。2食付きなら13000円というお値段であった。
それでもまだ金田一温泉郷の宿に於いてはお安い方であり、やはりボイラー加温しなければならない温泉宿は大変だと思うと、入る方も気を使ってしまう。
108.高繁旅館の黄金タイルとメノウタイル風呂
昨年ラル様に教えて頂いた、岩手・湯田温泉郷の湯川温泉にある高繁旅館、黄金タイル風呂へ要約訪れて参りました。
「黄金風呂」の看板通り、浴槽だけではなく浴室の壁までも黄金色のタイル貼りで、壁には戎さんと大黒さんの巨大タイル壁画がありました。
女性浴室の浴槽は、珍しい4つ葉のクローバー型の変形で金色タイル。
浴槽の中央からはボコボコと湯が沸き出ておりましたが、溢れ出しは全くないので、循環風呂ではあったようですが、塩素臭はしなかったです。
ジャグジーのためか浴場内はサウナ状態で、浴室中を眺めているだけでも暑く、温泉には1分ほどしか浸からずでした。真冬は良いかと思います。
男性浴場には広い浴室に、金色タイル浴槽が2つに分かれて在りました。
この黄金風呂とは別に更に広い大浴場があり、離れているので一旦着替えて行きます。
こちらの巨大浴場の壁には、岩手山ではなく富士山のタイル壁画が。
どうもこちらの館主さんは、黄金といい、戎や大黒や富士山と、何でも豪華日本一がお好きなようです。
そしてあったのが、何とメノウタイル風呂。黄金タイルも初めてですが、メノウ石のタイル風呂というのも初めてでした。
この円形のメノウタイル浴槽は、女性浴室にしか無いそうです。
この浴槽だけが掛け流しではないかと思われ、少ない投入量に比例した少ない溢れ出しがみられていました。
湯本温泉と共に湯川温泉も高温泉なので、源泉かけ流しは難しいところです。
大きな内湯からはザーザーと加水源泉が投入され続けていますが、溢れ出しなく循環泉。
露天風呂も併設されていましたが、こちらも明らかな循環で、塩素臭が無いとはいえ溢れ出しが無い湯船はがっかりしてしまいます。
泉質も湯本温泉と似通っており、ph7.0ですがナトリウム泉のためか、ヌルヌル感がありました。
観光ツアー等の団体客には良いかと思われる、大きな旅館の大浴場でした。
日帰り入浴は8:00~18:30 入浴料は300円。
湯川温泉には春山壮別館という、レトロタイル風呂を持つお宿もあり、入浴させて貰いたかったのですが長期休業中でした。
もう1軒春山壮本館というひなび宿が在り、こちらもおそらくレトロタイルではないかと思われるのですが、湯船の写真が見当たらず、もしかしたら造り直しているかもしれません。どなたかご存じの方写真送って下さい。
日帰り入浴を受け入れて貰えたのですが、時間が無く諦めました。入口をのぞいたら、地元のご老人が沢山玄関に腰を降ろしていられたので、きっと昔からの常連さん方で、入浴上がりなのだなと。
加水かけ流しのお風呂なのか?循環なのか?どんな湯舟なのか?春山壮本館と別館、また機会が有ったら訪れてみたいと思います。
湯川温泉へは、ほっとゆだ駅よりデマンドタクシー(湯川タクシー)が運行。
107.一休館のレトロタイル風呂
男所別タイル浴室の画像
106.一休館の見事な析出物のカランと哀愁ブルーが美しいレトロ湯舟
岩手、ほっとゆだ駅からは3つの温泉郷が分かれて在り、その一つがでめきん食堂のある巣郷温泉であり、あの見事に鮮やかなでめきん食堂のタイル風呂に入ってみたいのだが、コミュニティバスが週に一度、それも行けたとしても帰りは無いので、徒歩で行く事も考えたが、足を痛めている状態であり今回はパスした。
後の2つが湯本温泉郷と湯田温泉郷、これら3つが西和賀の温泉であるが、いずれも方向が離れており、各各のコミュニティバスを利用して向かう事になる。
もう少し秋が深まれば、紅葉スポットとして有名な錦秋湖が近くにある風光明媚な所でもあり、四季の移ろいと共に楽しめる温泉郷でもある。
今回宿泊したのは湯本温泉の一休館で、高齢の女将さんが出迎えてくれたが、ここの女将さんが、この地域をカタクリの郷として有名にさせたそうで、今では立派な観光ポスターとなり、カタクリが咲き乱れる中に一本桜が咲き、遥か向こうには残雪の山が見えている。この風景に出会うために来年の春にも訪れてみたいと思った。
「うちは源泉かけ流しですから。大きい所は循環ですけどね」と温泉には相当自身を持っておられるようで、何度も湯温を確かめに行っているとの事だった。
この地域の源泉は95度もの高温泉で、小さい湯船で源泉かけ流しの状態で入れるというのは難しい。投入口の湯量調節で?と思っていたが、宿から100メートル程離れた場所から6号源泉を引湯し、それを一旦宿のタンクに溜めてから、配管パイプ内が適度な湯温になっている事を何度も確かめてから、湯船に配湯しているそうだ。
「熱かったらかき混ぜて下さいな」と言われたが湯もみ板はなく、恐る恐る手を入れてみるがいけそうだ。ウ~ン熱め適温で加水無しで浸かれ、女将さん自慢の「ここだけ」という温泉は確かに気持ちいい。
湯船に浸かりながらふと見えたのが、赤い雪かきショベルで、どうやらこれが湯もみ板の代わりになるようだが、必要なかった。
浸かるとまず目を見張ったのが、少量ずつ投入されている源泉のカラン。
その周りには真っ白い析出物が、ふぐ提灯の様に尖った髭を毛やし、モコモコと盛り上がった白い物はプードルの頭の様でもあった。プードルにふぐ提灯が合体?という異質な例えになってしまったが、とにかくそれ位真っ白な析出物がこんもりと付着していたのを想像して欲しい。
温泉の析出物で、これ程までに見事になったカランを見たのは初めてだったので見飽きず見つめていた。
男性浴室では残念な事に、カランの析出物が削られてしまっており、あの見事なカランは現在は女性浴室でしか見られない事を、了承されておいて下さい。
「持って帰っていいですか?」と言った男性もいたらしいが、硬くて削り取れなかったそうだ。
外にでもあれだけの析出物が付着するという事は、配管パイプの掃除は大変だろうな。
そしてタイル湯船の湯底は、丸や角のターコイズブルーを基調としたつぎはぎレトロタイルで、一部パールが入ったタイルは、陽が当たると透明な湯に煌めき、美しく哀愁を帯びた湯船になる。
この湯底のタイルだけは比較的新しく(昭和30~40年代か?)張り替えられたタイルの様で、昭和20年代に造られたままの湯船の側面は、強固そうなレトロタイルであり、こげ茶色に変色していた。
湯縁の青緑の丸タイルも変色し、蛇の皮を思わせる様な同一色で無い美しさがあり、単一タイルでないところがとても味わい深く、良い味を出している湯舟であった。
床も豆タイルであり、全てがレトロタイルで残っている温泉というのは、貴重でもある。
また、この浴室は珍しく更衣室の床までがタイルで、明るいグリーンと白の市松模様の大きなタイルが用いられていた。
男性浴室も空いている時に見せて貰ったが、用いられているタイルは同じで同様のカラーだったが、湯船の容が四角く、女性の半円形の湯船の方が優しく好ましく感じた。
泉質はナトリウム・硫酸塩・塩化物泉で、僅かにラドンも含まれているので直ぐ温まり、浴後はしばらく暑いがその後は粗熱が取れたように引いていく。
ph7.6とは思えないツルツル感があり、タイル風呂のツルツル触りとマッチしていた。浴後は更に肌がツルツルとしていて驚いた。
シャワーも温泉で、硫黄?の様な焦げた様な温泉の香りがしていた。
レトロタイル風呂の美しさ、泉質の良さと共にとても印象に残る温泉であった。
今回は素泊まりで利用し、一人泊6150円は安い方では無いが、女性客は誰もおらず貸切風呂として利用でき、とても満足できた温泉であった。
コロナでもあり日帰り入浴は休止中であるが、ぜひ西和賀のそれぞれの四季と共に楽しんで頂きたい温泉宿である。
105.交互浴の佐久海ノ口温泉のタイル風呂
夏向き温泉で紹介させて頂いた、長野の佐久海ノ口温泉和泉館。
女性浴室に於いては、加温浴槽でレトロタイルが使われていた。
で、男性浴室はどんなのかと、空いている隙に覗かせて貰う。
宿により同一造りである場合もあるが、男性浴室の方がはるかに素敵な場合もある。と言うか、多いので・・。
こちらのお宿では、男性浴室のお風呂は円形だった。とてもすっきりした大きな円形造りで、縁だけがレトロタイル。円形のお風呂が何故か可愛く思うのは私だけだろうか?
加温源泉の円形の浴槽に、くっついた様にひょうたん型した冷泉風呂が並ぶ。これも可愛い。
どう見ても四角い浴槽が並ぶ女性浴室よりも素敵に見えたな。
どうしてこっちが男性浴室なんだろう?外から見えるとか?源泉に近いとか?
もしかして男性も円形風呂が好みとか?今度行く事があれば尋ねてみたいと思う。
両浴室共に、壁に使われたタイルがスッキリとモダンな装いだった。
104.加温循環が残念だけれど、男性のタイル風呂は可愛かった
新潟・五頭温泉郷の中の1つ村杉温泉は、驚異の30台マッヘを誇るラジウム温泉であるが、残念な事に泉温が25度程のため、共同湯含め旅館も全て加温循環している。
そんな宿の中でもひときわレトロ感漂う、あらせい旅館は昔ながらの湯治宿で、実際村杉温泉に出向いて見て、見つけた温泉宿だった。
五頭温泉郷観光協会のHPにも載っておらず、独自のHPは無く、当然旅行サイトには載っていない。
玄関口の鍵は開いているが、呼べども呼べども誰も出て来ないので「失礼しまあす」と言いながら館内へ。浴室を探し覗いて見た。
おー見事なタイル風呂。予感的中といったといったところで、このまま風呂に入りたい気持ちも起こるが、やはりそう言う訳にはいかない。
男女の浴室を覗いて見て、ここでもかなりの男女さがある事を知る。
玄関口に戻り、もう一度電話をかけてみたら、調度帰るところだと御主人が言われたので、待って入れて貰った。黙って男性浴室へ向かった。
やはり見るだけでは無く浸からないとね。
で、気づいたのが塩素臭がかなり強い、加温循環風呂だったという事。
それまではタイルに気を取られて、それらの事には余り気がいって無かったというお粗末さ。
出湯温泉の加温かけ流しや、源泉かけ流しの温泉にばかり浸かっていた自分には、久しぶりに塩素臭が強い循環泉に入って、というかほとんど温泉には浸からず、タイル浴室の写真ばかり撮って終わった。
この辺りの観光スポットの瓢湖の白鳥をデザインしたタイル壁画や、白鳥のオブジェなど、可愛らしい浴室である。男性風呂だが。
ラジウム温泉の蒸気を吸えば良いのは解るが、塩素臭と一緒に吸うというのはどうなのか?と思いながら後にした。
こうなってくると、改めて出湯温泉が素晴らしいものに感じる。
画像1.2あらせいの男性浴室 3.女性浴室
103.冷泉で有名な榊原温泉もタイル風呂だった
夏向き温泉で紹介させて頂いた、三重の榊原温泉は冷泉が有名で、浴槽内33℃程の冷泉はホント至福でした。無限ループが止まず。
大浴場は男女別になっており、それぞれに源泉の冷泉浴槽と加温循環浴槽がありますが、いずれもレトロタイルを用いた浴槽でした。
冷泉浴槽は、楕円形と角と言う様に容が違いますが、ブルー系で統一されたタイル風呂はいずれも美しく、加温された大浴槽の方は、ブルーのグラデーションに陽が射し湯面がキラキラし殊に美しかったです。
清潔感のある浴室は広いので、余り蜜になる事も無くゆったり入れ、浴場の美しさと快適さが相まって、女性には特に人気かも知れませんね。
広い浴場にタイル浴槽のタイルが、美しいままで残されているのが素敵でした。
日帰り入浴とは施設名と玄関口は違いますが、同じ浴室を使いますので、気軽に立ち寄って見る事もできそうです。
宿泊者のみ、近鉄榊原温泉口駅より送迎あり。
102.青森に残るタイル風呂~個室・布団付き休憩半日800円の温泉
まぐぞ―様のブログで知った玉勝別館。本館の温泉は日帰り専門施設であるが、宿泊専門施設である別館の温泉には、宿泊しないと入れないかと思いきや、個室休憩をとると誰でも利用できる。
驚いたのはその利用料金で、半日(9時~12時もしくは13時~16時)という3時間もゆっくりできて800円。1日なら1000円という安さ。
更に更にびっくりしたのが、何と案内された部屋(素泊まり部屋)に入ると、真っ白な洗い立てのシーツが掛けられた布団が敷いてあるではないか!
狭い部屋だが、テーブル・テレビ・お茶セットも付いており、床はオンドル。
今年は5月でも真夏日で、扇風機を出してくれたのだった。
その上嬉しい事に、洗い立て浴衣が用意されており、自分の持ち物で使うのはタオルだけ。
要するに時間内なら何度も温泉に入り、自由に布団で寝転ぶという至福な時間が、たった800円で与えられているという事だった。
申し訳ないとしか言い様の無いサービスで、貧乏性の私はとうとうその真っ新な寝具には横になれなかった。
さてその温泉というかタイル浴室。本館の温泉も利用させて貰えるのだが、別館だけにしたのは、まぐぞ―様のブログで拝見した浴室のタイル壁が、ひとえに美しかったからで、紺と白のデザインタイルが見事に並んでいた。
このタイルが浴室全体色々な部分に用いられており、アクセントタイルとしてドーム型の天井部にも使われている。
浴室の入り口はドームとなっており、ちょっとしたワクワク感があり、入ると期待通りの美しい浴場が広がる。とてもハイカラ感がある。
青森の浴室に於いてこのオシャレ感は珍しいのでは無いだろうか。
温泉はこの地方に多い単純アルカリ泉で、47.5℃の源泉が投入されており、セルフ加水となっているが、少々熱かったが加水無しで浸かれた。
汗が吹き出る。部屋へ駆け込む。扇風機の風に当たる。これを数回繰り返し、浴室のタイルに見惚れ、3時間が終わった。
玉勝温泉別館は上北町駅から徒歩2~3分程の所にあり、素泊まり2500円の温泉宿である。
始めに別館の方が建てられ、源泉は別館側にあるそうで、本館にも引湯しているそうだ。
別館の温泉を利用したい場合は、予約しておき、料金は本館で支払ってから別館に入るというシステムになる。
こんな感激の温泉が地方にはまだあるのだなあと驚き、是非再訪し今度は布団も利用させて貰おうと思った。
101.残雪の岩木山と巡ったタイル風呂⑨出町温泉公衆浴場
青森市内にある出町温泉。地元民に人気の公衆浴場であるらしく、とにかく綺麗な温泉施設である。入浴料450円。
浴室に入ると前面の壁一面、浴槽の上に東北の海の風景が描かれたタイル壁画があり、それにも増して目を惹くのが、浴槽の中央にあるまるで鳥籠の様にも見える物だ。
近づいて見ると、細かいタイル造りのドーム型の源泉投入口かと思いきや、湧出しているのは冷水だった。
とても不思議で、後で尋ねたら「これで湯温を自動調節している」という優れものセンサーである事が解った。こんなのがあるとは初めて見たし、知った。
では源泉は何処から❓というと、おそらくジャグジー部からか?
常時ジャグジーが噴射し、浴槽から溢れ出す温泉は、浴室の床を流れ広がって行く。
少しぬるめの小さな浴槽と2つに仕切られており、41℃の単純アルカリ泉が掛け流されているが、ジャグジー効果もあってか、汗がなかなか引かない良く温まる温泉でもある。
浴槽内は水色のレトロタイルで、湯縁は黒の細長タイル。なかなかこだわりの浴室でもある。
浴室の円柱もタイル造りで、仕切り壁にはブロックガラスも使われていた。
広い洗い場にはバネ式カランが40基もあり、その上には固定式のシャワーが付いている。こちらも温泉のようである。
レトロ感もありながら、非常に清潔感があり、明るく綺麗な浴室は、人気の程が解る温泉である。
前に広がる海のタイル絵を眺めながら湯に浸かっていると、まるで海にでも浮かんでいる様な気にもなる、ゆったり爽快な温泉であった。
100.青森に残るタイル風呂~ドバドバぬる湯の姉戸川温泉
青い森鉄道小川原駅に降り立つと、すぐ前に温泉の看板を目に出来る。公共交通を利用の自分には、駅近なのは凄く嬉しい。入浴料250円。
温泉名が姉戸川という何か女性的な名からなのか、入り口の縦字で書かれた看板と、赤く大きな温泉マークがレトロ感と女らしさを醸し出している?様にも思える。
しかし入ってみると、浴場は青森に多い広い浴室に、簡素な長方形のゴツイ浴槽がひとつ・・。
湯縁は石で槽内は水色角タイル張りであるが、温泉成分でその色は失われ、よどんだものになっていた。浴室の床も薄茶色・・。
写真で目にしたグリーンの色は温泉の色では無く、広く浅い寝湯の湯底部分のコンクリートを、緑色に塗ったその色だった・・。
何だか武骨感が強い浴槽である。
この浴槽の特徴として、源泉投入口が打たせ湯となっており、ドバドバ投入。
湯温を下げるためかと思われたが、そうでは無くもう1つある投入口からの源泉とほぼ同じで、どちらもぬるめの湯だった。
青森の温泉に於いてぬる湯は珍しく、ゆっくり広い浴槽でゆったりと、他の人を気にする事なく浸かっていられるのが良い。
体感的に38℃~39℃の温泉は長く浸かって居ても熱くならず、春や秋には調度良く、冬は寒いのではないかと思えたが、何の事は無い。上がったらポカポカポカポカしていた。
もう1つ特徴的なのが天井で、おそらく天然木板に(木に付着した微生物?もしくは温泉成分?)かと思われる淡い美しい水色の縞模様を呈す、その高い筒型の天井に見とれていた。
この天井はここでしか見られないものでもあるなあ・・。
天井の淡い色合いと、壁の白タイルにシャワー台は紅のタイルというコントラストが美しく、この辺りが女性的で姉戸川温泉の名にふさわしい感じがしたりして。
そして何より湯が、ヌルヌルの単純アルカリ泉の優しいぬる湯。
などと、変わった温泉名に、無理やり女性らしさをこじつけていたが、多分そんな事には全く関係ない、この姉戸川と言う地区にある温泉施設という事だけなのでしょう。
99.珍生館のドバドバ加温源泉かけ流し、1時間の至福
新潟、五頭温泉郷の1つ出湯温泉にある珍生館。自家源泉の単純放射能泉は驚異の20.8マッハ有り、最大のポイントは、ドバドバ加温源泉かけ流しの湯を、貸し切り風呂で1時間堪能できる事だ。
投入口は鯉の口であり、加温源泉を余すところなく勢い良く吐き続けている。
源泉温度は36℃であり、それを41~42℃程に加温した源泉が、浸かるとタイル浴槽からザザーッと溢れ出す。
2階に在る浴室は、陽光が射し明るい。そして透明な湯に、タイルの湯船が清々しい。
湯底は白の丸タイルが、側面は水色の角タイルがびっしりと並び、欠けも剥がれも無くとても美しく、清潔さが感じられる浴槽である。
ラジウム温泉を快適に楽しみたい、という方にはピッタリかも知れない。
ph8.0台のラジウム泉自体にはヌルツキは無いが、おそらく身体に付いた微泡で、ヌルツキ感が感じられるのだろう。とても新鮮さが感じられる湯であり、浴後は肌スベスベとなる。
長く浸かって居たいがさすがラジウム泉、すぐ温まり暑くなってくるので、浸かったり腰かけたりを繰り返し、ドバドバ吐き続ける加温源泉、溢れ出て行く湯を見つめていた。何とも勿体なく感じてしまう。
そうだ。トドってみようと思い立ち、程よく身長サイズの浴槽に並び仰向く。
ラジウムの湯気で寒くも暑くも無かったが、何せ1時間限定の貸し切り風呂という入浴制限があるので、心ゆくまでという訳にはいかない。
そこが珍生館の温泉の難有る部分で、入浴は17時~21時の間。
泊まり客が重なると、1組1時間1回だけは調整で予約時間に入浴し、他は空いていれば入れるという事になる。宿泊客が自分だけだと良いが、限られた時間で空いていればというのがなかなか難しい。
そして翌朝使用できるのは、1階にある小さな浴槽のみで、これまた希望時間に合わせて1回きりの入浴となる。
おまけに、1人だと2連泊以上しないといけないのだが、上記時間以外の入浴については、つまり昼間は2軒ある共同湯に、自費で入りに行かない限り温泉には入れないという事になる。
う~ん・・厳しい入浴制限がある宿なのだな。何せボイラー代がかかるし、かけ流しだからな。
その不自由さを感じの良い女将さんが「不便掛けてすみません」と言いながら、できる限りの融通を利かし対応してくれる。
何だか連泊している意味が無いみたいなのだが、華報寺共同浴湯といういくらでも長湯できる、ぬる湯の素晴らしい共同湯が目の前にあるから、そちらで温泉を楽しんでおれば良いのかも知れないけれど・・
まあ、個人の考え方次第だと思うが、やはりあのドバドバ源泉かけ流しの湯が、明るく美しいタイル浴槽に満ち溢れ、それを貸し切りで味わえるというのは、この宿にしか無くとても惹かれてしまう。
尚、日帰り入浴は行っておらず、冬季休業有り。
98.とうとうここまで来てしまったか・・咲花温泉柳水園
新潟・咲花温泉は月岡温泉と同様色のグリーンが美しい温泉だが、こちらは昔から自然湧出していた温泉である。
各宿は集中管理した温泉を引湯しているが、宿泊先に選んだのはタイル風呂を目的とした柳水園で、60年程前からの宿だそうだ。
楽天の評価(3.台を普通ととってはいけないのは解っていたが)や、ブロガー様のコメントを読んで来ていたつもりだったが・・
柳水園へ向かう坂道では宿の廊下側が見え、エッ?廃屋?営業しているのだろうかと、宿泊予約を入れているものの不安になる。
外観古びて寂寂のコンクリートの建物の扉を開けると、不愛想に女将さんが立っており、暗い館内の2階の部屋へ案内された。
部屋の中央には布団が敷かれ、ロッカーを開けると太いロープが無造作に入っているではないか!何コレ❓首・・な訳は無いだろう。多分避難ロープなのだろうけれど、怖くなってロッカーは直ぐ閉めてしまった。止めて欲しい。こんな所にロープを入れるのは。
ハァ・・気を取り直して窓の青もみじを見つめる。縁側の緑色のクッションが新緑のもみじに似合っている。唯一この風景に心和んだ。
気を取り直し何はともあれ温泉へと、廊下へ出るとトイレ臭が籠っている。
和式トイレだった。利用時は浴衣の裾が床に着かない様に気にしなくてはならないので困る。
浴室は1階にあるが、この廊下もトイレがある為トイレ臭がしていた。フゥ・・
男性浴室の扉が空き誰も入っていなかったので、風呂を見せて貰う。男性と女性では浴室に大差がある所も多いので念のため。
エーーッ??コレは・・?目を疑った浴室の壁。
モダンアートでは無いよな?
自然洞窟をイメージしているとかでも無いよな?
濃いグリーンの部分は、古いカーペットが膨らんで剥げて来ている?のでも無いよな。
よおく見てみると、ただのタイルが剥がれたままで、壁の地肌が剥き出しとなり、苔の様な緑の部分は硫黄成分で・・と言う事の様だった。しかし、これ程凄い無残な浴室を見たのは初めてだった。
もしや女性浴室までも❓いやこれは男性浴室だけであって欲しいという、淡い願いは裏切られ全く一緒だった。イヤイヤこれはちょっと・・
女性浴室においてはおまけに、洗面台の鏡があったのだろうと思われる場所が、大きく穴が空きホゲており、周りの壁が膨張し歪み膨らんでいる。
タイルが剥がれ腐蝕した壁には、苔の様に緑がまとい付き・・恐ろし過ぎる。
昼間だから入って入られるが、夜は怖くて入られ無い。
呆気に取られしばし浴室を見回していたが、この宿へ来た目的がタイル風呂だった事を思い出した。
四角い浴槽の槽内は紛れも無くタイルであった。真四角のタイルがきちんと並び、元の色は何色か解らないが(後で聞くと水色だそうだ)色違いのタイルも混じり、それらが鉛銀を帯びた様に見えるのは、温泉成分のせいなのだろうけれど、緑の透明な湯に美しく沈んでいる。
そして、何よりも美しいのは温泉の色。それは宝石と同じエメラルド色だった。
熱めの湯に身を浸し浴室を見回すと、とうとうここまで来てしまったかと、我ながら感心した。行きつく所まで来てしまった様な気がする。これ以上の浴室は無いだろう。
それにしても平日というのに結構部屋が埋まっていたのは、県民割や併用できる市民割のためか。それにしてもこの浴室を見て驚かない者はいないだろうし、泊まり客はきっと男性の温泉マニアだろう等と思いながら、腐蝕した壁を見回していた。
投入口には、鯉を体に巻き付けたションベン小僧の彫刻が立っている。そして踏んづけられた鯉の口からは熱めの源泉が投入されている。
バックの壁を前にして立つションベン小僧は、1枚のアートの様でさえあった。
横には飲泉用のコップが置かれていたので口に含んでみると、最初は歯がギシギシする様で酸っぱいのかと思いきや、微かに玉子味がした様な気がしたと思ったら、何の癖も無い飲みやすい温泉になった。不思議だったので、何度か口に含んでみたが同じだった。
咲花温泉6号と書かれた温泉成分表には、一般には無いイオン名がずらっと並び、昭和初期に書かれた適応症には、やはりリウマチや神経疾患などの難しい病名が上がっていた。
泉質名は、含硫黄-ナトリウム・塩化物-硫酸塩泉となっていたが、微量鉱物を多く含む珍しい泉質であるようだ。
柳水園では48.3℃の源泉をそのまま掛け流しているが、浴槽内は43℃弱位に感じ、長くは浸かっていられず湯縁に腰かけ、綺麗な色の温泉と壁を交互に眺めていた。
湯を見つめていたら、ふと読んでいた戦争本の事を思い出した。
「仲宗根政善作 ひめゆりの塔をめぐる人々の手記」この本は日本国民全員が読むべきだと思うし、プーチン大統領始め各国の大統領にも読んで貰いたい本だ。
100年も前の事では無い戦争中には、日本の何処かではこんな温泉が湧いていた所もあったのだろう。身体を拭くどころか飲み水さえなかった戦時中にさえ・・もし戦火の中こんな温泉が見つけられたら、どんなに狂喜したことだろう・・戦争はたった数十年前に起こっていたのだ。
壁がどうのこうのという問題では無い。温泉は温泉で素晴らしいのだから。
いや、話が大きく外れてしまった。
夜は入られないだろうと思っていた温泉へ夕方も入ったが、24時間掛け流しの湯は夜になっても人を呼ぶのだ。
あの翠の湯に惹かれ、怖さを超え夜にも入った。歪んだ扉を開けると硫黄の香りが強く感じられる。
恐ろしいと思っていた壁にも慣れると言ったら良いのか、でも壁は余り見ないようにし、エメラルドの湯に浸かった。
もしこの温泉が、白のタイル浴槽に囲まれていれば、もっと別物になっている位に美しいだろうな。
しかしいつまで持つのだろうか?この浴室は。などと思いながら温泉を愛しむ様になって来ていた。
翌朝、玄関口で女将さんに温泉の事を聞いていたら、ふいにガタンゴトンと列車が走る音がした。磐越西線のレールが宿のすぐ横を走っている。という事は土日に走るSLを見られるという事でもある。
宿の広い庭には桜の木が多く植えられていた。桜とSLの写真にエメラルドの温泉が重なる。
あれ程避難していたのに、思わず「桜の時期はいつですか?」と女将さんに聞いていた。
97.残雪の岩木山と巡るタイル風呂⑧山田温泉と良く似た倉庫の様な光風温泉
光風自動車工場の並びにある倉庫の様な光風温泉は、実に山田温泉と良く似た雰囲気で、こちらは正面の大壁高くに、剥げかけたえびす様と寅が描かれている。
広ーい浴室の壁周りに、バネ式のカランだけが並んでいるところも同じだ。
長方形の大浴場も同じで、少し茶緑っぽい透明湯である事も、泉質も津軽に多いナトリウム・塩化物が多い炭酸水素塩泉で、物凄い溶存物質量も、非常に良く温まる寒い青森に適した源泉であるという事も。
おまけにこちらは更衣室までオンドルで暑かった。
ツルツルとしたその泉質の良さは良く解るが、素っ気ない浴場に、2つに仕切られた素っ気ないタイル風呂と、所々茶色く変色した床。
そして光風温泉の青塗の壁には点々と黒カビも見られ、レトロと言うより寂れ感の方が強いが、見かけより質。何より温泉の質。源泉かけ流しの熱めの湯であるという事が大事。
そんな感じに伝わってくる温泉であった。
近くに屏風山温泉もありそちらにも行って見たが、修理(リフォーム?)中で中期の臨時休業中だった。
96.残雪の岩木山と巡るタイル風呂⑦本格レトロな森田温泉でトドった
陸奥森田駅近の森田温泉。久しぶりに出会う本格的なレトロ風呂に感激した。
年代を経て床に広がるタイルが、温泉成分で元の色も判り辛く変色し、全体に琥珀色を帯びている。
浴室には黒いタイル壁を用い、黒い湯に、浴槽もヒビが入った黒タイル。
湯縁にだけ用いられた白細長タイルがラインとなり、なかなかスタイリッシュな浴室だ。
しかし温泉成分に寄り、湯船の中の丸タイルは完全に茶色となり、浴室全体が茶色っぽく染まり、かなり渋いイメージが強い。
青森にまだこんなタイル浴室が残されていた事に感激した。
ボコボコと泡だつ熱めの源泉が、黒い湯の上を白い泡波をたてながら滑り、次から次へと溢れ出て行く。
一瞬客足が途絶えた。まさかのチャンス。豊富に溢れ出す温泉の横に身を携えトドった。
壁詰めの細長い浴槽は、調度1人だけがトドれる場となっている。
静かで暗っぽい浴室には僅かな陽が射しこみ、ボコボコと温泉だけが湧出を続けている。
あ~この温泉と浴室が永遠であればなあと願う。
このサイトで知り得たこの温泉に感謝。しかし、青森は特に温泉の廃業が多く、嫁がれて以来ご主人が発掘した森田温泉を守って来られた女将さんも、お元気ではあるが90台半ばの超高齢者となられており、この温泉の行く末はどうなるか解らない状態となっている。
レトロ温泉ファンの方はお早めに訪れを。
95.残雪の岩木山と巡るタイル風呂➅レトロと言うかかなり古い山田温泉
弘前から五能線で、残雪の岩木山と調度咲いていたリンゴの花を眺めながら、津軽平野を走るとこの辺りはつくづく、りんご畑と田んぼばかりであるなと思う。
水田に映る逆さ津軽富士や、リンゴの花と岩木山のコラボが写真に撮れて嬉しい。
この沿線にある藤崎町はふじの発祥地でもあり、弘前は青森りんごの本場である事が良く解る。
鰺ヶ沢へ向かうこの路線には多くの温泉が存在し、津軽が温泉天国である事を伺わせるが、地元の方達にとってはそれは日常で、当たり前の事として温泉は存在して来たのだろう。
そんな中でも昔のままの姿を保っている山田温泉は、陸奥鶴田駅から徒歩で10分程。
まず目に付くのはネオンの看板で、これはレトロの象徴でもある。
入浴料330円。雑多なロビーと全くやる気なしの従業員の方・・
目にした浴室は、光風温泉とうり2つの様なというか、この地方に多い広い倉庫の様な大浴場。
入ると浴室全体が巨大なサウナ状態。65,2度の源泉を加水し、熱めとぬるめの2つの浴槽に分けられ、それぞれに加水用の蛇口も付いている。
熱い方の湯船は当然無理だったので、温めの浴槽にそのまま浸かってみると、すこぶる気持ちが良い。
メタケイ酸は231㎎と多く、この地方に非常に多い成分総計5761㎎のナトリウム・塩化物泉の温泉は、浴室に居るだけでも汗が出て来る。
コンクリート造りの湯縁には、よく見ると析出物が固着。
腰かけ部分には丸タイル、湯底は柄タイルを使った浴槽に、茶色い透明湯が満たされている。
広大な浴室には25基のバネ式カランと、一部にはガラスブロックも使われているが、浴室の壁タイルは茶色っぽく変色し、鏡は錆びれ、かなりの年季を感じさせる。
正面の高い壁にはこれまた光風温泉と同じ様に、ペンキで巨大な絵が描かれているが、こちらは絵本の様な可愛い絵だった。
全体にかなりレトロと言うか古い。だが泉質は良いので、寒い時期には地元民の方達の大切な温泉となるのであろう。
寒い冬にはピッタシの源泉が、何故かこの地方に多い泉質である事は、不思議に神様がそう与えてくれたのかと思える様な源泉が、そこかしこに湧出している津軽。
94.残雪の岩木山と巡るタイル風呂⑤不思議色の桜ケ丘温泉
弘前市内からでも岩木山は臨め、津軽のシンボルとしての存在が良く解る。
弘前駅からバスで30分程の桜ケ丘温泉は、住宅地の中、老人ホームの裏側にある。バス停より3分の道中では、保育所の子供達が散歩している姿にも出会う。
極一般的な銭湯といった感じの小奇麗な浴室で、入浴料も銭湯並みなのか、加温循環のためなのか390円で少しお高め。
珍しかったのが温泉の色で、紺鼠色の濃い濁り湯で、地獄谷温泉・後楽館の湯を思い出したが、こちらの方が灰色が濃いかな?しかし、投入口からの温泉は透明なので、鮮度等により湯の色合いが変わる様だ。
というのも、こちらの地方では数少ない硫黄が入っている温泉で、硫黄の香りがする。
泉質的にはナトリウム・塩化物泉で良く温まる湯だが、舐めると非常に複雑な味がした。
塩と鉄の味がし、酸っぱい様な感じもするがph7.9。
何と、湯底に触れると指先が黒くなっていた。
浴槽はブルーのタイル張りでおそらく槽内もそのままのタイルだろうと思うが、濃い濁り湯のため良く解らなかった。壁にはタイルと合わせ、淡いブルーでスッキリとした市松柄のライン。
特筆しておきたいのが、画像1のコテコテシャワー口と、見えにくいが真っ黒になったバネ式カラン。いずれも硫黄成分によるものであろうけれど、これらは創業当時からのものなのだろう。リフォームされた浴室には不釣り合いと言うか、レトロな存在を保っていた。
93.岩木山と巡るタイル風呂③弘南鉄道弘南沿線の温泉
弘前駅から走る弘南鉄道弘南線の館田駅。車窓からでも、降り立った駅からでも岩木山が眺められます。
館田温泉は駅から徒歩で5分程の所にあり、建物にもタイルが使われており、レトロ感が垣間見えます。食堂も有る日帰り温泉施設かと思いましたが、宿泊もできるとの事でした。
入浴料400円を支払い温泉へと思いますが、番台の女将さん?が物凄く話好きと言うか、人恋しそうと言うか、暇を持て余していると言うか、興味津々で色々尋ねて来られます。
タイル風呂が好きで探して来たと言うと「えっ?何処もタイルじゃないの?」とびっくりされるのに、こちらの方もびっくりしてしまいましたが「そうですねえ 銭湯とかって多いですよね」と合わしながら、そうかー 確かに青森って、昔からそのまま地元にあるという温泉が数多く、特に津軽地方は温泉天国。
そうなんですよね。青森には断トツタイル風呂が多いと思います。そのままだったらレトロタイル風呂ばかりの温泉地になっていると思います。
ただ今では、多くのタイル風呂がリフォームされていて、浴槽は現代の味気ないタイルに変わってしまっているのです。
それがまだ昔のままで残されている温泉を探して、見つけた1軒がこの館田温泉だったのですよと言う事ですが、女将さんは不思議そうな顔をしておられました。
で、入った温泉ですが明るく大きな浴場で、2つに仕切られた大きな白いタイル浴槽には手すりも付けられており、湯縁に貼られた桃色レトロタイルがとても可愛かったです。床の所々にも桃色タイル。そして壁にはガラスブロックも在り。
泉質はナトリウム・塩化物泉で溶存物質は5000㎎以上あり、熱めの源泉は加水され提供されていますが、良く温まる温泉は、寒い青森では大モテの温泉でしょう。
外には、タイル風呂では無い露天風呂と水風呂も併設されており、この日は5月でも25度越えで暑かったので、私は井戸水の水風呂と、熱めの温泉の交互浴が気持ち良く、此処は通年イケる温泉であり、庶民に愛される様に造られている温泉なのだと思いました。
フロントには、ゲージに入れられた猫(保護猫)が数匹飼われています。好きな方には嬉しいですね。
92.残雪の岩木山と巡るタイル風呂③板留温泉の映像として残る浴室
板留温泉民宿はせ川。電話で、3時以降なら日帰り入浴可能との返事を貰い、伺った温泉では女将さんと御主人が迎えてくれました。
入浴料300円を支払う前から、御主人が丁寧に応対して下さり、お風呂場へ案内し「誰も来ませんのでゆっくり入って下さい」と御親切に言って下さいました。
さてその浴室ですが、床だけはタイル張りであるという事は写真で見て来ていたのですが、写真で見るよりウンとスッキリしたとても美麗な浴室で、まず床の鮮やかなグリーンの丸タイルが光ります。
それとコントラストに用いられているのが、壁の紅タイル。
壁全体は一般的な大きなタイルですが、白では無く枝豆色というこだわり。
そこにアクセントとして紅色タイルでラインが描かれています。
更に壁を這う配管パイプも、こげ茶色という心配り。
そして写真では材質が良く解らなかった浴槽は、石造りだと思われます。大きな石を削って湯船にしたものでは?石のざらつき感や、一部は素材の石のキラキラも混じっています。色は淡いベージュで、丸みを帯びた縁が優しい。
大工さんのセンスを詰めた、こだわりの浴室なのではといった感じがします。
これらの美しさが詰め合わされた浴室の温泉は、一目見た瞬間からとてもトキメイテしまいました。
そう、それが頭の片隅にずっと残るんですよね。
同じくもう1つずっと気になっていて、泊まってみたいと思っているのが、鶯宿温泉の民宿とちないですが、浴室・浴槽が珠玉だと、何だか料理まで小奇麗で美味しいのではと、勝手に想像してしまい、いつまでも気になってしまいます。
板留温泉は、集中管理された芒硝泉の配湯ですが、此処の浴室の狭く密閉された構造上なのか、温泉という香りが感じられ、扇形の小さな浴槽に満たされた湯が、浸かるとザァーッと溢れ、それは気持ちの良いものでした。
こうしたこじんまりとした温泉には、湯治宿として利用し好きなだけ出入りしたいところですが、源泉が熱すぎて加水調整(温泉を止めたり出したり)が必要な様で、難しいところです。
浴室は30年程前に造られたものだそうで、御主人曰く「石?ただのコンクリートでしょ。割れて来て接着剤でつぎはぎですよ」と言われるのですが、私的にはどう見ても石造り。さてどちらでしょうか。
冬の板留温泉に再訪し、民宿ささきと合わせて民宿はせ川も、泊まってみたいと思わせる浴室を持つ温泉宿でした。
91.残雪の岩木山と巡るタイル風呂②もてなし料理が凄い板留温泉民宿
弘前から弘南鉄道に乗り、岩木山を眺めながら黒石へ。今回初めて行った板留温泉で、宿泊した民宿ささきは3代目のお宿だそうで、綺麗な女将さんと御主人でもてなしてくれました。
時に猫ちゃんも顔を覗かせてくれますが、館内に猫臭は全く無いので、臭いの心配はありません。
この宿を選んだのは、タイル風呂と、私の愛猫が同じ赤トラだったからという私的な理由だけだったのですが、泊まってみて驚いたのがその料理の凄さ。
大きなお膳に載せられて2階まで運ばれて来た夕食は、宿泊客1人のためにこれ程の御馳走をと、恐縮する位の感動もの。
ご飯はピカピカ、朝夕ともに炊きたて!夕食が凄いと朝食ががっかりという宿も結構ありますが、此処はそんな事はありませんでした。
それと、料理の好みを聞いてくれるのと、魚はどちらの魚にしますか?など、選ばせて貰えるのが嬉しかったです。
やはり泊まるとなると、料理というのが楽しみになりますが、私が今まで泊まった宿の中で、コスパを考え合わせた料理の凄さで1、2番の宿になりました。(もう1軒は鶯宿温泉鶯泉館)
さて温泉の方ですが、板留温泉は1箇所から湧出している源泉を、各宿が引湯しているのですが、高温のため加水してから投入されているので、残念ながら香りも色も浴感も温泉らしさを感じられず・・
そもそも芒硝泉の香りというものが、私には良く解っていないというのもあります。
ただ良く温まる、サッパリしキリットした熱めの温泉で、何度か出入りする温泉、ビジネスマン向きというイメージしか。
そんな温泉だったのですが、御主人が非常に湯加減に気を配られていて、できるだけ客好みの湯温で入って頂こうと、調整して下さっていたようであった事だけは解りました。
翌朝入った時には、籠っていたのかやっと焦げた様な温泉の香りがしたような気がしました。
浴室は1つで、もう1つは小さな家族風呂もありましたが、そちらは主にご家族で使われている様でした。
タイル浴槽の中は、紺色丸タイルと薄いグリーンの角タイルで造られ、所々昔ながらの絵タイルが混じっています。
残念なのが湯縁の黒い大きなタイルで、これがもっと違った色合いの、例えば鮮やかなグリーンとか他にマッチした鮮やかな色のタイルであれば、浴槽全体がもっと違った印象になるだろうなと思って見ていました。
3階建ての館内にはあちこちに洗面台があり、ちょっと雑然としたところが民宿的でもありましたが、女将さんは部屋が寒く無いか等色々気を使って下さったり、帰る時には御主人がそっと、リンゴジュースと御煎餅の手土産を差し出して下さったり・・お二人のもてなしがとても身に沁みるお宿です。1人泊2食付き7500円。
宿の前には、新緑と川の美しい風景が広がっていますが、冬にはこの景色が信じられない位に激変するのだろうな。雪に覆われた風景も見てみたいなと強く思った温泉宿でした。
90.残雪の岩木山と巡るタイル風呂①嶽温泉でトドる
岩木山麓の嶽温泉。数件の宿が在り、硫黄の白濁湯ばかりかと思っていたが、タイル風呂を持つ西澤旅館は、熱めの透明湯だった。
嶽温泉の源泉は岩木山中腹から湧出し、数キロ引湯したものを一旦タンクに貯めているのが、ぬるめの白濁源泉。もう1つは、岩木山麓より湧出した熱めの源泉をタンクに貯湯。この2つのタンクより各宿へ配湯している。
西澤旅館は熱めの源泉を多く引湯しており、水道(山の湧水)蛇口から好みで加水して浸かる。確かに熱めだったが加水せず浸かってみた。
酸性泉だがとってもなめらかな湯で、メタケイ酸も200mgを超え、ツルツルとしたとても気持ち良い温泉だった。
浴槽はレトロタイルという程の物でも無いが、20年程前のものだそうで、赤茶色の角タイルで湯船の淵どりがなされ、浴槽の中は水色タイルだった。
創業時はイチョウ型のタイル風呂であったそうだが、リフォームの際その様にタイルを貼ってくれる大工さんがいなかったので、長方形になったそうである。
浴槽から溢れる湯を見て、ふとトド寝を思いついた。
平日の温泉。誰も来ない。トドってみた。
20℃越えの5月。窓から入る爽風の心地良さ。静けさ。もう起き上がる事ができないくらい気持ち良い。オンドルに寝転んでいる感覚。
天井は少々カビっているが、そんな事はどうでもよい。白濁硫黄の他の嶽温泉にも入りたかったが、それもどうでも良くなった。
パ~パパ~と夕刻を知らせる、哀愁あるサイレンが唱歌を奏でる。
多分あの、小学校と中学校を合併し、新しく建てられた校舎からだろう。窓には「ガンバレ ガンバレ」と貼られていたな。
トド寝しながら郷愁に誘われていた。
GW明けの5月では、嶽温泉一帯の桜並木は終わっていたが、まだ水芭蕉が名残を留めていた。残雪の岩木山が直ぐそこに。
とても美味しい嶽キミ(とうもろこし)は8月~9月一杯が収穫期。是非食べに来たい。
西澤旅館は山菜中心の郷土料理で、1人泊2食付き7850円。登山口が近い。
89.自家源泉の極上湯、山梨・湯村温泉郷のタイル風呂
昭和レトロ感が街のネオンにも残っている、山梨の湯村温泉郷。
此処の温泉の泉質は非常に素晴らしく、しかもどのお宿も自家源泉を持っているという。
共同源泉の配当という温泉郷が結構多い中、各宿が自家源泉を有している温泉郷というのは貴重だと思う。
配湯と自家源泉、一旦タンクに貯められた温泉と、湧出したての温泉とでは、やはり新鮮さが違うのか浴感が違う様に感じてしまう。
タンクからの引湯では、更にその距離が問題となってくる様に感じられるし、更に温泉地によって管理方法使用方法が違うので、温泉の権利以外に使用量を購入しなければならないお宿では、使用時間=入浴時間に制限が設けられてしまう。なので何といっても、24時間自家源泉かけ流しという温泉が最高の贅沢になってくる。
その湯村温泉の泉質は、ヌルヌルだけれどアルカリ性単純泉では無く、ナトリウム・カルシウム・硫酸塩泉であり、非常に浴感が柔らかい。
私が好んで利用する旅館明治の湯は、ベールをまとう様な泡付きと、フワフワ感が有る極上湯。そして41℃程の熱すぎない湯温なので、気持ち良くゆっくり浸かって入られる。
というか、女将さん曰く「いつ上がったらいいのか解らない」とお客さんが言ったそうで、確かに上手く言い得て妙であると私も思った。
余りに気持ち良いので、上がるのに踏ん切りを付けないといけないと言うか、いつまででも入っていたいというか、上がりたくない温泉なのだな。
浴槽内はレトロタイル、そして以前にも書いたが、旅館明治の女性浴室の壁は、ブロックガラス(拍子木の様なオレンジと透明のガラス)が隙間なく1つずつ大工さんの手に寄って張られた半円形造りの壁で、裏のライトに照らされて、湯が黄金の様に煌めく。
確かに煌めいていた・・のだったが、最近訪れる度に、ガラスタイルを照らす裏のライトの灯りが消えて行き、黄金の湯の煌めきが徐々に暗く・・
私は女将さんと御主人に「全国何処の温泉に行っても、このガラスタイルで造られた浴室の温泉は、2つと無いのです。とっても貴重でとっても大切ですから」と、何とか保存をお願いしたいと勝手な希望を伝えるのだけれど・・
「古いので、何処もかしこも直さなければならないところがあちこち出て来て・・」と、息子さんが継ぐ訳でも無さそうな温泉宿は、自分達の代で終わらせようかとも考えておられるようで、修理費用もままならない浴室の灯りなど、果たしていつ灯るやら・・
復旧どころかこのまま消え去って行く事も有り得るかもで、とってもとっても気になる。
明治時代に建てられたので「旅館明治」だそうで、現在5代目の飄々とした御主人と、明るくおしゃべり好きな女将さんがもてなしてくれる、コスパも良い宿。1人泊2食付き8950円。
館内の至る所にレトロ感が在り、磨かれた板張りの床が美しい。
男性大浴場は総タイル造りで見事。比較的新しいのでまだまだ綺麗。
太宰治が好んで入った温泉というだけあって、確かにお湯は良いので是非お薦め。あと、太宰治にご興味おありの方にも、資料が沢山揃えられております。
そして湯村温泉でもう1軒、タイル風呂を持つお宿を見つけました。
ホテル吉野。こちらもレトロ感を残すお宿で、男女ともにタイル浴槽。
男性浴槽は大きく、ブルー系のタイル。女性浴槽は小さく、淡い緑っぽいベージュ系のタイルで、共にレトロ角タイルで造られています。
明るく清潔感がある浴室で、源泉投入口の岩は温泉成分に寄り緑に発色し、それも合わせて綺麗でした。
浴感は旅館明治に比べ、ややあっさりした感じでしたが、浴室そのものの違いからかも知れません。こちらは動力揚湯の自家源泉で、湯量は少なめ。
それぞれのお宿が自家源泉を持つ湯村温泉。他にも弘法の湯など何処も泉質が良いので、若干の湯の違いや浴室の違いなど、湯巡りを楽しんでみるのも良いかも知れないですね。
画像1.2ホテル吉野 3.旅館明治
88.秀麗な鳥海山が目の前に見える宿もタイル大浴場だった
冬季に秋田へ向かう便で、飛行機の窓から見た鳥海山の美しさに惹かれ、以来何度か訪れた鳥海山麓。
春は山形側から、鳥海山をバックにした桜並木を見、新緑の頃はレンゲツツジとシマシマの鳥海山の素敵な景色の中をハイキング、秋には竜ゲ原湿原へ。
他にも何度か足を運び、鳥海山周りの観光スポットへも行った。
次は夏に、8合目の鳥海湖まで登山したいと計画中。
今回は、桜と由利高原鉄道と鳥海山という風景を見たくて訪れたが、あいにく曇りで鳥海山は裾野しか見えなかった。
そんな中でも、一番多く宿泊しているのが鳥海荘(鳥海山荘ではない)
鳥海荘の前身が国民宿舎であった為、宿泊価格が非常にリーズナブルで、私がいつも泊まるのは、旧館に3室だけあるお得なお部屋。1人泊2食付きで6870円ながら、料理は新館泊の人と同じ旅館料理。
更に鳥海荘は部屋と料理が別価格になっており、料理は頼まずレストランで食べるという事も出来るので、便利でもある。
お宿のまん前にはデーンと鳥海山。秋田側からの鳥海山なので三角の綺麗な姿が見られる。
部屋からも、ホールからも、レストランからも、そして露天風呂からは少しだけれど見える。
何度も泊まっていたが、今までは特にタイル風呂に興味があった訳では無かったので、まさかタイル風呂だとは思ってもいなかった。
大浴場全体が白の総タイルで出来ていたのだった。タイルはシンプルに3種類で、床や浴槽はレトロ角タイル。浴槽の中全てがレトロ丸タイル。壁は普通の白い大きいタイル。
浴場の中は広く大きな内湯の他、寝湯やジェットバスや水風呂や休憩スペースまであるが、いずれも白の総タイル造り。豪華と言うのか、ちょっと味気ないと言うのか・・白一色。
そこに淡いグリーン色っぽい温泉が綺麗。残念な事に循環泉であるが、塩素臭は無くナトリウムの香りがし、浴感はとってもヌルヌル。成分総計4090㎎のナトリウム・炭酸水素塩泉であり良く温まる。
内湯からは鳥海山は見えないのだが、手前の小さい方の露天風呂からは、立つと塀越しに鳥海山の頭が見える。
以前は、旧館の浴場が源泉風呂で貸し切り利用できたが、使えなくなってしまっていた。
送迎も現在は、矢島駅のみとなり時間も指定される様になってしまった。
残念な事が増えてしまったけれど、鳥海山は変わらない。
由利鉄沿線の桜は調度満開だったのに、残念な事に鳥海山と桜を一緒に見る事はできなかったけれど、美麗な鳥海山に会いに、由利鉄に乗りまた訪れる日があることだろう。
87.タイル風呂の宝庫かも!?鶯宿温泉➅あさひの湯源泉
岩手・鶯宿温泉郷は8の字型に広がっており、交わる部分に在る桜の広場を真ん中に、左手側の多くの宿が杉の根の湯を使用し、右手側はあさひの湯源泉が配湯されている。他1軒は独自源泉を使用。
今まで述べて来た宿は全て杉の根の湯源泉であったが、あさひの湯源泉も入り比べてみた。
しかし結果的には、はっきりとした違いは判らず。
1軒は、ニュー鶯泉閣で、浴場は広く四角い小さめのタイルで埋められた浴槽であったが、レトロタイルとは言えない、タイル面がザラッとして滑りにくくなったペッタンコタイル。
展望風呂と銘うっているが、展望できるのは浴槽の僅かに両端のみ。
温泉は投入口付近には多くの湯花が見られ、あさひの湯は湯の花が多いのが特徴なのかと思ったが、そう言う訳でも無いようである。源泉タンクに近かったのかも知れない。
2軒目は、あけぼの荘。浴室全体が白の総タイルで造られている。
壁は白い普通の大きな角タイルであるが、浴槽や床は白のレトロタイル。
白いタイル浴槽の中で、湯が淡く蒼っぽく見え、小さい湯花も見られた。
40℃程のぬるめの湯は、加水され投入されているのかも知れない。
そのためかアルカリ性単純泉だが、ヌルツキは無し。せめて硫黄臭があればなあと思った。
最後、杉の根の湯源泉の民宿栄弥。こちらは源泉タンクからかなり離れて在ったのか、温泉はぬるく湯華も無く、間抜けた感じの湯だった。同じ杉の根の湯でもこれだけ違うのかと驚いたのだった。
男女で浴室が違い、男性の方は大きく、浴槽の端部分にレトロタイルが残っていた。
女性浴槽は小さく、花柄模様のタイルが使用されていた。
4月下旬の鶯宿温泉郷はまだまだ早春の装いで、水仙がやっと咲き出し、桜は蕾だった。
鶯宿温泉郷には所々多くの桜の木が植えられ、GWには見頃となり温泉と桜を楽しめる郷となるだろう。
その頃には合わせて、小岩井農場の1本桜も見頃になるのだろうな。雫石から見る岩手山と秋田駒ヶ岳は、残雪に覆われ美しかった。
画像1.あけぼの荘 2.ニュー鶯泉閣 3.民宿栄弥の小さな女性風呂
86.タイル風呂の宝庫かも!?鶯宿温泉⑤えーっこの料理で6000円台
鶯宿温泉の中でも特に湯が良いと、温泉備忘録様のブログに書かれていた鶯泉館。
冬に予約した際も一杯で宿泊できず、かと言って日帰り入浴は「宿泊客優先」という事で受け付けて貰えず、春の今回は、早くから宿泊予約をいれました。
岩手・雫石辺りはまだ早春で、期待していた桜は蕾。代わりにカタクリの花が、鶯宿温泉郷の土手のあちこちに咲いていました。
鶯宿温泉では鶯の付く宿が多いのでややこしいのですが、ここ鶯泉館の湯は多くの宿で使われている杉の根源泉。この同じ杉の根の湯を使用している宿であっても、どうしてこんなに湯温や湯華が違うのか?源泉位置(引湯距離)に関係ないのは何故なのか?と不思議に思っていたのですが、やっと理由が解りました。
杉の根源泉を3つのタンクに分けて引湯し、更にそのタンクから各宿へ配湯しているそうで、鶯泉館はこのうちの1つのタンクが宿の裏山にあるので、源泉に近い高温で比較的新鮮な温泉が湯船に投入されていたのです。
しかも湯底注入で激熱。水道水をしばらくジャバジャバ出し、かけ湯を繰り返しようやく浸かりました。
単純アルカリ泉なのに玉子臭の良い香りがし、糸くずの様な湯華も浮かんでいます。熱いが気持ち良い湯です。
スッキリした浴室は、紺色の壁タイルがアクセントになり、床の花柄模様のタイルに囲まれた、湯船のタイル模様はシンプル。
男性浴室では、壁のアクセントタイルがグリーンになり、床タイルの色も少し変わります。
どちらかと言うと女性浴室の方の配色がスッキリと綺麗かな。
温泉からあがったら、各部屋の前にはスリッパが並んでおり、平日であるのにほとんどの部屋が埋まっているのにびっくり。
何故こんなに人気なのかと思っていたら、運ばれて来た夕食にびっくり。
カサゴの唐揚げやお刺身に天ぷら、旬の筍やほや貝、たっぷりの大きな浅利が入った吸い物など、山と海の新鮮な食材が並び、豪華でとても美味しく感激!これで1人泊2食付き6750円でした。
同じ日に泊まられていた方達はビジネス客でしたが、おそらく地元民には料理が良くて安いで有名の温泉宿。あの真冬でも一杯だったのだから。
女将さんも親切で好印象。宿泊予約はお早めに。
85.美ヶ原の美しタイル浴室
長野・松本の美ヶ原(うつくしがはら)温泉にあった美しいタイル風呂。
入った2軒の温泉宿のタイル浴室の特徴として、小さな角タイルを用いてグラデーションを描いている事。これは今まで入ったタイル浴室には無かったもので、とても上品で、和の配色というか着物の様なというか・・
これだけの細かなタイルを手仕事で貼られた大工さん、大工さんのセンスは凄いなあと感心。そしてそのレトロタイル浴室を、美しいまま守られているお宿にも感心。
①丸中旅館の見事に美しく広いタイル浴場-写真1
広い浴室の壁の一部細かい四角タイルのグラデーションで、扇子の様にヒダが造られ、投入口の周りを囲むタイルと合わせ、扇の様な雰囲気を装っている。
壁や浴槽合わせて、約30種類もの色・形違いのタイルが使われており、華やかさがある。
この見事な浴室は男性浴場で、空いていたのでどちらでもと言われ、入らせて貰えたが、女性浴室の方は作り直したのか、がっかりのタイルなので、是非男性浴場へ入って頂きたい。宿泊すると交替で利用するようだ。
旅館で日帰り入浴を受け付けてくれる宿は少なく、丸中旅館は16時~20時、600円で利用させて貰える。
②女性的な可愛いタイル浴室の御宿石川-写真2.3
浴室は2つあり、どちらもこじんまりとした浴室で、どちらもピンク系タイルを主体とした浴室である。
1つは昭和30年代に造られた浴室で、丸中旅館と同じく細かい四角タイルを用い、ピンク系でグラデーションを描いた壁は、上品な感じがし、とても綺麗に保たれている。
もう1つは新しいタイル浴室だそうで、壁のピンク柄タイルはもしかしたらタイルシート?なのかも知れない。
浴槽内は水色の丸タイルだったので、こちらは以前からのレトロタイルの様だった。
日帰り入浴は受け付けておらず宿泊したが、料理がとても美味しいお宿であった。
美ヶ原温泉は、源泉を集中管理し配湯(民家、旅館含めて60数件へ〕しているそうである。そのためph8.0台の温泉ではあるが、残念ながらヌルヌル感は無く無味無臭のアルカリ性単純泉であったが、松本の市街地からとても近い温泉地なので、立ち寄るには良いかも知れない。日帰り専門入浴施設も在る。
84.静岡ののどかな鉱泉2種~その②重厚感ある竹倉温泉みなくち荘
静岡の温泉と言えば伊豆。こちらは賑やかであるが、同じ静岡でも先に述べた平山温泉や、この竹倉温泉はのどかな感じが漂う、秘湯感ある温泉というか鉱泉である。
女性的であった龍泉荘のタイル風呂に比べ、こちらは男性的と言える、みなくち荘のタイル風呂。
湯自体が黄土色の濃い濁り湯である為、そちらにばかり目が行って、タイル風呂だと写真では気づかなかったが、よく見るとどうもタイルであるらしいので行ってみた。濁り湯にタイル風呂は珍しい。
何と天井以外はタイルという、重厚さを感じる立派なタイル浴室であった。
全てが丸タイルで統一されている浴室は、温泉成分で変色したのか、そもそもこんな鋼色のタイルであるのか、触ってみないと解らない位の渋さが光る丸タイルが、びっしり並び創られている。こんなシックなタイルには初めてお目にかかった。
壁にはオレンジ色のタイルで、太く流れる様なデザインが何本かされており、モダンさが光る浴室である。粋な大工さんだったのだろうと思う。
さて、湯は鉱泉を加温し循環であるそうだが、塩素臭は無く加温かけ流しかと思ってしまったが、そう言われると溢れだしが無い。よく見ると小虫や髪の毛が浮かんでいるので、洗面器で救い出してから浸かる。
見た目からでも良く温まりそうな湯は、とにかく良く温まり、少し浸かっていただけでも、浴後は汗がにじんで来る。
鉄分が含まれているのだろうと思うが、金気臭は無く、口に含んでも鉄臭さは無かった。
「冬はとってもいいのよ」と常連さん。勿論そうだろうと思う。
窓の外には畑が見え、陽が入りのどかな感じがする。熱海や伊東の喧騒からはかけ離れた、のんびり感が心地良い。
「日曜だけど、今日はお天気がいいから皆お出かけしているのね」と、入浴客の少なさを言われ、成程そうかも知れない。予想外に静かでゆったり浸かれた事を喜んだのだった。
昔はこの辺りには3軒の温泉宿が在ったそうだが、残ったのがこのみなくち荘だけだそうである。日帰り入浴だけになり、料金は600円。
83.感じの良い若女将さんが接客する、穏やか感ある温泉の円いタイル風呂
ずっと行ってみたかった静岡・平山温泉龍泉荘。昭和33年開湯し昔は宿泊もしていたそうだが、今は日帰り入浴のみのため、青春18切符を利用し、デマンドバスも予約し、やっと念願叶った。
静岡は桜が早いので訪れた時には名残桜になっていたが、おそらく3月末~4月初旬なら満開の桜が迎えてくれるだろう。そんな素朴感とのんびり感が残るお茶の里に、その温泉は在った。
急な下り道を降りて行く。道の端には荷物専用の細いケーブルの様な物があるが?
鄙びた建物の中は小奇麗になっており、手作りの土産物が並び「私が作ったんです」と受付に立ってらっしゃった綺麗な娘さん?若女将さん?が。
3時までなら食事も出来る様で、1日此処でゆっくりとできるようである。こちらは若御主人が担当しているようで、お二人とも明るく感じが良い。
入浴料500円を払い、貴重品や大きな荷物は預かって貰う。
浴室に入ると硫黄の香りが漂ってくる。くっきりとしたピンクと水色の丸タイルで造られた円形の浴槽が、とても可愛いく綺麗である。男性浴室は紺と水色タイルだろうか?
濁りは無い単純硫黄泉で、白い消しゴムカスの様な湯華が舞う。
中央にある岩の投入口からは加温源泉が投入され、3つに仕切られ段々にぬるくなって行く最後の浴槽から、少しずつ溢れ出て行くようになっている。
自分の好みの湯温の浴槽に浸かり、ぼうっとできる温泉だ。前面のガラス窓からは、穏やかな田舎の風景が広がる。新緑、竹林、橋、茶畑・・のどかな感じがいいなあ。
湯に浸かりながら壁に貼られたものを読んでみる。
御殿乳母温泉の由来には「戦国傷士を偲ぶ秘湯」と書かれ、平山温泉乳母小唄では、この温泉が駿府城の石垣建設に携わった村人達が、汗を流した400年余りのひめゆ(秘湯)である事。また、河鹿のうたが聞こえると唄われていた。
今も前の川で河鹿蛙が、鳴くのかどうかは定かでは無いようであるが、のんびり感は残っている温泉である。
帰りにも若女将さんは丁寧に接客してくれ、訪れていた男性客は何だか鼻の下が伸びている?様な、そんな微笑ましい温泉は男性客にもすこぶる人気なのであろう。性差関係なく感じが良い接客態度に感心した。
降りて来た急階段をキャリーバックを抱えて昇る。「大変だな」と声をかけてくれたおじさんは、何か音がし振り向くと、あのケーブルに乗って下って行くではないか!?。
なーんだ・・人が乗れる様になっていたんだ。常連さんでないとちょっと解んないな。扱い慣れてないと乗れるかどうかも。
今度訪れるとしたら、食事も摂り乍らゆっくり温泉を楽しみたいが、その時にはこのケーブルもチャレンジしてみようかな。
82.伊東温泉梅屋旅館、残念な事に名物の塩湯が・・
昨年の熱海の災害でこの辺りも被害を受けた様で、梅屋旅館名物の地下にあった塩湯の配管?源泉槽?が壊れ、塩湯が使えなくなってしまったとの事。
伊東温泉にあって非常にレトロな梅屋旅館は2つの浴室があり、その1つが伊東の高温源泉に、梅屋旅館独自の冷泉の塩湯をセルフでブレンドし、自身の好み湯温に調整して入るのが何とも心地良いとの評判だったのですが・・残念。災害にはかないません。
という事でもう1つ有る、50年程前に造られたレトロタイル風呂にだけ入って来ました。
どちらの浴室も鍵をかけて入る事ができます。
しかし熱い!水道水をジャバジャバ加水して、果たして温泉はどれ位入っているのか?
そうかこのあったかいのが温泉だと納得して、一応温泉に浸かっている気にならせましたが、無色透明無臭の湯は温泉らしさも無く、ただ熱かっただけでした。
こちらのタイル風呂は、湯縁等にアクセントの紅色タイルを用い、湯船内は水色角タイル、壁は暖色系のタイルで造られていました。
古いだけあって湯縁のタイルは剥げて来ていましたが、それは御愛嬌かな。
宿自体もかなり古く、トイレだけはウォシュレットに改装。
この宿で、素泊まり1人泊5550円というお高め料金は、熱海や伊東温泉価格に並行しているのだなと思いました。
81.タイル風呂の宝庫かも!?鶯宿温泉④湯の花舞う民宿けむやま
煙山旅館の看板が残る民宿けむやまは、同じ杉の根源泉の引湯だが、此処は違っていた。薄茶色の湯の花が一杯なのだ。そして浴感も円やか。
何故同じ源泉の引湯で、この様に違うのか不思議だ。
杉の根源泉から川向こうにある、清光荘や民宿とちないや石塚旅館は熱めであるのに比べ、源泉側ではあるがやや高台に位置する、民宿けむやまはぬるめとなり、更に高い場所に位置する民宿栄弥は、更にぬるかった。
そして湯の花が見られたのは、何故か民宿けむやまだけだった。
浴室は小さな家族風呂といった感じで、湯縁の青~緑の古い丸タイルには、白い析出物が付着したり、タイルが剥げてしまっていたりと、レトロ感いっぱいだ。
浴室内にはパイプが走り、2つある温泉だか水だかのカランも真っ黒。
源泉は湯底注入と、ホースからも僅かずつ投入されており、湯船の縁から静かに少しずつ溢れ出ていた。
そして、落花生色のまるで皮がむけたかの様な湯の花は、余り気持ちが良いものでは無いが、こじんまりとしたタイル湯船の中をあちこち舞う。
温めの温泉と浴感の心地良さに、今回入った鶯宿温泉の中では、ここの湯が一番気に入ってしまった。また訪れた際には是非立ち寄りたいと思う。
日帰り入浴200円。残念ながら宿泊は素泊まりのみである。
80.タイル風呂の宝庫かも!?鶯宿温泉③タイル使いが見事な清光荘
浴場の紺と白のストライプの床が印象的な清光荘。こちらの浴室は男性浴場だが、この日は男性の宿泊客が無かったので、日帰り入浴客の使用時間帯以外なら使わせて貰えた。
紺と白の丸タイルが整然と並び、見事な縞模様を描いている。そして驚いたのは、排水溝迄が水色の丸タイルで造られていた事。
浴槽内もブルーの丸タイルで、壁は男女浴室共に、深緑の細長い竹の様なタイルが詰まっている。
きっとこの浴場が造られた当時は、かなりオシャレであったと思われる。
女性浴場は画像3で、男性浴室の方が断然素敵だが、どちらの浴室もタイルの欠けが無く、綺麗な浴室だった。
温泉は24時間掛け流しで、杉の根源泉を引湯しており、やや熱めのサラリとした感じの温泉は、ラドンも少量だが含有しており冬でも湯冷めしにくい。熱めの温泉は長くは入っていられないので、何度も入りに行った。
単純アルカリ泉の透明な湯は、タイル風呂にはもってこいの湯で、鶯宿温泉だけでもあちこちの宿で、それぞれのタイル風呂が造られている。それは大工さんのセンスに由るものか、施工主の依頼に由るものか解らないが、宮大工が造った部屋がそれぞれの趣向を凝らしている様に、レトロタイル風呂の温泉も、使われているタイルの色や形や組み合わせが、様々あってとても楽しい。
今回宿泊した清光荘の建物は、コンクリート造りで古く、部屋はややカビ臭く、石油ファンヒーターは3時間毎に切れる為、その都度延長ボタンを押さなければならないのが面倒臭かった。勿論トイレはウォシュレットでは無い。
これらを辛抱できれば、コスパが良い宿で料理も良く、浴場の気持ち良さを言えば、鶯宿温泉の中でも上位に挙げられる。女将さんも親切なので、建物だけが残念だが、簡単に建て替える訳にはいかないだろうから・・。
79.タイル風呂の宝庫かも!?②郷愁誘う石塚旅館
温泉逍遥様のブログで、桜と共にある石塚旅館の写真を見て以来、絶対ここに行きたいと思って来ましたが、宿泊依頼をしてもコロナでなかなか受け入れて貰えなかったり、こちらから遠慮したりして来ました。
しかし桜を待つまでに、タイル風呂が多く存在している鶯宿温泉へ行きたくなり、冬でしたがやって来ました。
鶯宿温泉郷はかなり細長く、宿が広範囲に渡っていましたが、徒歩で周れない程では無く、雪道をグルグル行ったり来たりしました。
そんな中で石塚旅館は、温泉街のほぼ真ん中辺りにある、まるで小学校の校舎の様な横に大きな、昭和初期に建てられた木造のお宿でした。
前の道路側には桜の木が植えられており、その桜が咲いた頃にはますます校舎の様に見え、だから郷愁を感じる宿だったのですね。
今回は日帰り入浴でお邪魔したのですが、ホントお邪魔感が半端無く・・。
日帰り入浴は受け入れされていたのですが、如何にも県外から来ていますと言う格好の私をすんなりとは受け入れて貰えず、御高齢の女将さんは「ウチなんか古くてタイルは剥げているし、シャワーは無いし、お湯がぬるいから、もっと大きくて綺麗な所へ行かれた方がいいと思いますよ」と頑なに拒まれ、しばらく押し問答が続く。
コロナで県外客は受け入れしていないと言われたら、まだ諦めが付くのだが、そうでは無いと言われるので、ならばこちらも鶯宿温泉で一番入りたかったここの温泉に、何としても入りたいので粘った。
そして、女将さんの方が諦めてくれて、入れさせて貰えたのだった。
静かで広い木造の館内も浴室も、とても清潔に保たれている。
鶯宿温泉には、3つの源泉があり、各宿はそれらの源泉から引湯している。一番多くの宿が引湯しているのが杉の根源泉で、石塚旅館もそうであった。
女将さんはぬるいと言っていたがそんな事は無く、やや熱めの湯が掛け流しで、小さなタイル浴槽を満たしていた。
確かに浴槽は湯縁のタイルなど、かなりかなり剥げている部分が多い。と言うよりも、残ったタイルが辛うじて張り付いている風だった。
しかし湯船の中の、グリーンと白の市松模様になった、小さなモザイクタイルはとても可愛い。
角部屋となる浴室は浴槽に見合わず広く、壁が低く窓から陽射しが入り、とても明るい。
清潔さと穏やかな明るさが満ち溢れた浴室に、小さな年季の入ったレトロタイル風呂が静かに佇み、欠けたタイルからたゆまず流れ出て行く源泉に、安堵する時間が流れる。
石塚旅館はやはり、外観も館内も浴室も何か郷愁を誘う温泉宿であった。
日帰り入浴料200円。素泊まり湯治宿となっているが、要予約で食事も提供してくれるとの事。
鶯宿温泉街には桜の木が所々植えられている様で、春にも是非訪れてみたい温泉郷となった。
78.タイル風呂の宝庫かも!?鶯宿温泉①息をのむターコイズブルー
民宿であるが、岩手・鶯宿温泉の観光ポスターにもなっている、民宿とちないの温泉は、息をのむ位に美しい、ターコイズブルーの丸タイルで、湯船の内側全てが造られている。
中でも特に目を惹いたのが、湯船の中の排水口。どこにでもある黒のゴム栓がしてあるのだが、その周りのタイルが円錐の様に滑らかに美しく、窪んでいっている。こんなのを見るのは初めてだった。
透明な温泉は共同源泉だが、湯底注入されているためかやや熱めで、他の鶯宿温泉に比べ新鮮に感じる。湯底注入の良さを実感したのは、ここが初めてかも知れない。
床は茶色のタイルで花柄を描いており、湯船の縁は黒の石造りだが、それもターコイズブルーのタイルをキリッとまとめ上げており、トータルな美しさは女性好みの温泉宿かも知れない。
また、仕切り壁にはガラスブロックが使われていたのも嬉しかった。
浴室へは階段を3階半、上がらなければならないが、それでも良ければと確認が入り、300円で日帰り入浴をさせて貰えた。
更衣室には暖房器具も置かれており、良心的である事が伺える。
接客も良く、こういった宿は食事も美味しい様な気がする。
あの美しいタイル風呂が、頭の片隅に残って仕方ないので、いつか必ず宿泊してみたいと思っている。
77.鳴子温泉郷のタイル風呂
レトロタイルの浴槽はアルカリ単純泉の様な透明の温泉に多く、それに比べ鳴子・東鳴子・鬼首・中山平・川渡の5つの温泉からなる鳴子温泉郷は、濁り湯が多いためかタイル風呂は少なく、コンクリートの浴槽が多いような気がします。
全部合わせて60近い温泉がありますが、sro201様、鳴子温泉郷全踏破されましたでしょうか?私はまだ半分程度ですが、入った温泉を思い出してもどうもタイル風呂が浮かばず、要約見つけたレトロタイルの温泉、2軒だけ紹介します。
他にあれば教えて下さいませ。
1軒は、見つけたと言うよりも、何度も行っていましたが気付かなかった、東鳴子温泉のいさ善湯。
このサイトでも紹介させて頂いている、混浴の浴場の一部がレトロタイル造りでした。
何だかレトロ感ある雰囲気がいいなあと思ってはいたのですが、仕切り壁や柱、浴槽周りの床等にはモザイクタイルが。
でも浴槽自体はコンクリート造りかな。湯が黒いのでタイルが見えないし・・。
大浴場にはガラスブロック壁や、柱等にもタイルが貼られていましたが、コンクリートの大浴槽に圧倒されて、目がいってなかったです。
もう1軒もこのサイトに載っている阿部旅館。こちらのお宿は2種類の温泉、2つの浴場があり、どちらの浴室でも、浴槽でもタイルが用いられています。
浴槽周りの壁は、茶系のやや大きめのタイルで、浴槽には白いタイルが使われていましたが、年季が入っており、かなり剥げて欠けているのが見受けられました。渋い色の温泉に見合った渋いタイルでした。
無色透明の温泉では無いので、どうしても綺麗な色とか、可愛いタイルとかは用いられていなのは、仕方ないかも知れませんね。
レトロタイルの温泉を探して周っていると、どうしても単純アルカリ泉の湯に入る事が多くなり、そうすると湯の華から遠ざかってしまっていました。
なので、阿部旅館ではタイル風呂でありながらも、大きい湯華も見られて、久しぶりだったので何だか感激しました。
76.新潟・瀬波温泉開湯の湯のタイル風呂
一度訪れてみたかった、日本海沿いにあり夕陽が綺麗な瀬波温泉。中でも、開湯の宿としてある大和屋旅館は、海沿いではありませんが、海岸までは徒歩で5分程。
なので、雪原の浜辺に足跡を残して来ました。真っ白な雪にズボッと足を踏み入れたくなる方、きっと皆さんもそうでは無いかと思いますが、これはどういう欲求なのかなと思いながらも、誰も足跡を付けていない雪を踏みしめて来ました。
ハイ、大和屋旅館の温泉ですが、タイル風呂に見えたので行ってみました。
う~ん確かに浴槽にはレトロタイルが用いられており、壁の滋味なタイルと合わせ、昔感ありました。
源泉かけ流しをうたっている宿なので、熱めの源泉が、冬は気持ち良かったですが、湯面ばかりが熱くなっているので、湯もみ棒等があると良かったかもです。もしくは窓の一部でも開けておいて頂けるといいんじゃないかと思いました。
ナトリウム泉で良く温まり、熱めの湯がお好きな方には良いかと思います。
部屋のトイレが非常に狭い男女共用型のトイレでしたので、宿泊はお勧めできません。浴室近くのトイレも和式が多く、ウオシュレットは有りませんでした。
やっぱり折角海辺の宿に訪れたのだから、オーシャンビューをという方には、他に多くの循環泉のホテル(もしかすると源泉かけ流しの宿もあるかもです)や、多分民宿もある様だったので、そちらをお勧め致します。
画像3は、新潟と言えば稲田。広ーい広ーい田んぼが真っ白な雪原になり、そこに境が解らない位に覆いかぶさる様に分厚い雲が・・これが新潟の普通の冬空なんだそうです。でも僅かにでも晴れ間が広がると、真っ白な雪がダイヤモンドの様にキラキラ✨
75.国登録有形文化財の宿のタイル風呂
新潟県五頭温泉郷の出湯温泉にある清廣館は、昭和初期に建てられた木造3階建てのレトロなお宿。遠目でも、窓ガラスの揺らぎが手延べ板硝子だと解り、薄い灰色に見える鄙びた木材は年季を感じさせ、黒く墨文字で書かれた清廣館の看板がどっしりと迎えている。この秘湯を守る会の宿にもタイル風呂があった。
浴室は2つで、男女日替わりで使われる。1つは浴室全体が木材で造られ、桧の浴槽は小さめだが檜の香りが残っている浴槽。
もう1つが紺の丸タイルを基調とし、部分的に水色のタイル、アクセントに煉瓦色の石を用いた、洗練されたタイル風呂で、まだ新しく造られたかのように、1つのタイルの欠けも無く美麗だ。
温泉は自家源泉を加温しての湯底注入で、ぬるめだが弱放射能泉なので、冬でも良く温まる。
料理も良く、何よりレトロ感ある落ち着いた角部屋がとても気に入った。
ハニカミ屋さんの女将さんと、対照的に社交的な御主人と、お料理担当の大女将さんらの家族経営で、文化財である温泉宿を守られている。
出湯温泉には3軒の温泉宿が在り、他にもタイル風呂がある宿も有るので、また是非訪れてみたいと思う。何より大好きな華報寺共同浴場がある。
五頭温泉郷とは、出湯温泉・村杉温泉・今板温泉の3つをいい、村杉温泉には温かめの共同湯があるようだ。
近くには月岡温泉や、観光では瓢湖や福島潟、新潟憩いの森や五頭連峰登山など、ちょっとした楽しめる場所もあるようである。
74.新潟から珠玉の共同湯2選②癖になる新津温泉
新津温泉の看板が見え、駐車場に近づくと遙か50メートル以上先の建物からだろう、異臭が放たれてくる事に気付く。凄いな、これは噂通り、いや噂以上の強い匂いである。
外でもこの匂いなのだから、中は物凄いだろうと案じながら、番台で400円を払い入口へ。
受付のおじさんは気さくで話しやすそうな良い感じ。
建物の外観からして、手書きの効能書きの看板がレトロ感満載だったが、中に入ってもペンキ塗りの扉や、ぶら下がっている看板が昭和感あり、微笑ましい。
浴室に入り浴槽に目をやると、何とタイル風呂では無いか。
新津温泉の写真では、楕円の様な形をした浴槽が印象的で、タイル風呂とは思っていなかっただけに感激。
浴槽内が丸タイル造りになっていて、湯底は明るいグリーン、腰かけ部分や側面は薄茶色の丸タイルだった。
湯はかなりトロリとしており、黒い小さな湯花が、投入口の網から漏れ出たのか浮かんでいた。
さて油臭だが、鳴子温泉や月岡温泉の様な香りでは無く,ここの油臭は独特で、木の香りが混じっていて、油臭の中にもスーッとした感じがあり、初めての香り体験であった。鼻が慣れたのかどうなのか、外の異臭の様な感じは全く無く、直ぐ馴染めた。
40℃弱とぬるめだがナトリウム成分で温まってくる。この温泉の成分、溶存物質が何と1万越え。メタホウ酸が400㎎以上もあるという特別な値に驚く。実に希少な濃厚温泉であると思う。
香りも成分も破格である温泉が、タイル風呂であった事が嬉しく、更に帰りがけ番台のおじさんより「コロナが終わったらまたゆっくりおいで」と声をかけられ「ハイ!」と返事した自分は、こんな斬新な温泉に浸かれた事に、この日1日ルンルンしていた。
73.新潟から珠玉の共同湯2選①華報寺共同浴場
初めて入った時、その美しさに感動し、頭の隅から離れなかった、五頭温泉郷の出湯温泉にある華報寺(けほうじ)共同浴場。
偶然入ったその共同湯は、みすぼらしき(失礼)湯小屋とのギャップが凄く、まさかこんな美しい浴槽が密やかにあったとはと、驚いたのでした。
浴槽の周りは大理石で造られており、その白い湯縁の中には透明な温泉が満たされて。
湯船の内側壁は水色の細長タイルで、四角く型どられた、湯底のグリーン系のモザイクタイルを二重囲いし、何だかとても上品で綺麗なのです。
浴室の床は赤色暖色系のモザイクタイルで、広さ、明るさがある浴室は、湯小屋からは想像できなかった雰囲気。
番台の方に「とっても綺麗です」と言ったら「綺麗なのにはそれなりの理由があって、365日毎日湯を入れ替え、清掃しているのよ」とのお言葉でした。
250円の入浴料で、早朝6時~19時迄毎日営業して下さっているという有り難き温泉。
朝の6時に行ったら女性は誰も入って来られずでしたが、男性浴室からは常連さんか?2,3人来られているようでした。
湯は単純弱アルカリ泉で、薄く泡付きもある柔らかいぬる湯で、ラジウムも含有されているので、冬でも温かいです。
加温しながら湯船の中央の湯底から注入されており、結構な湯量が投入されていました。
崖になった岩の上には弘法大使様が奉られている、1400年も前から湧き出て来ている有り難き、お寺の温泉なのです。
私が思いつく中で、タイル風呂の共同湯の中では、美しさで言えば1位かな?
72.北海道・北見の24時間温泉、夢風船
北見市にある塩別つるつる温泉と一羽の雀の間にある、滝の湯温泉・夢風船は、24時間自動(無人)温泉で、自動販売機で400円の入浴券を買い、無人窓口に置かれているプラスチック容器に券を入れて、浴室へ向かいます。
以前は滝の湯センターと言い宿泊施設でもあった為、館内は広く飲食も出来る無料休憩所もあります。
無人と言っても綺麗な館内に、綺麗な浴室。ドライヤーも置かれていました。
浴場も広く明るく、半円形の大きな湯舟と、扇形の小さな湯船が有り、床は花柄モチーフになったベージュのタイル。
湯船の底には、明るいパステル調の色合いのレトロタイルが用いられ、優しく綺麗でした。
嬉しい事に、仕切り壁にはガラスブロックも使われていました。
温泉は勿論、ツルヌルのph9.6あるアルカリ泉で、一羽の雀と同源泉ですが、こちらは僅かに湯華もあり、大きな浴室に広い浴槽は、気持ち良いものですね。
夢風船の特徴は、何といっても24時間オープンという、車中泊の方にはとっても便利な温泉であるという事。珍しいんじゃないでしょうか?
すぐ横はキャンプ場でもあり、蛍も飛ぶ小さな公園もあり、車で10分程行けば道の駅おんねゆ温泉・山の水族館もあります。
バリアフリーでもある浴室は、要予約で10時~11時家族風呂として、1000円で浴場1室を貸し切れるそうです。地域の住民にも、ライダー達旅行者にも優しい24時間温泉ですね。
でも清掃って、いつしてくれてるのかな?って思ってしまいましたけれど・・。
71.帯広・本物のモール泉巡り➅丸美が丘温泉ホテル連泊
ホテルが多い帯広・十勝川温泉の中で、ここだ!と決めたのが音更にある丸美ヶ丘温泉。
泉質重視で探していたところ、温泉備忘録様のブログを読み直ぐさま連泊を決定。初めての温泉宿で連泊は冒険でもあるのですが、結果的に大正解。素晴らしく気持ちの良いお湯でした!
写真の通り、展望窓に面してとっても広い浴槽があり、42℃程の黒っぽいモール泉が掛け流され、浴槽の3分の1程がジャグジーになっています。広さがあるので人と人が重なったりする事無く、ジャグジーの中でゆっくり手足、身体を伸ばせます。
浴槽中央辺りのラッパ型の投入口から、ドバドバと源泉が放射状になり投入され続けています。大浴槽に於いては何といってもこの付近が一番新鮮なモール泉を味わえます。腐植質は6.0台という、私が入った帯広温泉モール泉の中では最高値。浴場全体に何と表現して良いのか解らない香りが充満しており、きっとこれがモール臭なのだと思いました。
そして、丸美ヶ丘温泉へ訪れる方のほとんどが、こちらの温泉目的でしょう。それは右端にある小さめの浴槽。37℃程のこの温泉が抜群に気持ちが良い!超極上湯なのです。
湯舟の端からプクプクと気泡が上がっています。泡付きはこの付近だけでなく、湯船全体何処で浸かっていても、身体に気泡が付きます。
と~っても柔らかなぬる湯は、まるで羊水に浸かっているかの様。夢見心地で眠ってしまいそうになります。心地良さだけではなく、体の芯から温まり、ぬる湯でありながらジワジワ汗がにじんできて、浴後は、身体がポカポカポカポカしているのを実感しました。
まるで子宝温泉かの様で、妊婦さんも多くいらっしゃってましたね。
また、神経痛などの痛みにも非常に良く効き、私はこの頃苦しめられていた痛みが、この温泉に入ってやっと軽くなりました。
冬場だったので、42℃の大浴槽との交互浴をしましたが、ぬる湯の方は出られないくらいに心地良かったです。
もう1つの素晴らしさは、広~い全面ガラス張りの展望風呂で、前は林。季節毎に自然の素晴らしさがある様で、冬場は立ち枯れた木であるが故に、夜は音更町の夜景が楽しめ、朝は朝焼けが楽しめました。勿論、新緑も最高だろうし、紅葉も見られるそうですし、リスも見かけました。
宿としては素泊まりのみで、1人泊4700円でした。
ただ一つ難点と言えば、日帰り入浴が10時~23時まであり、宿泊しても23時で終了です。
翌朝の6時半~だけが僅かにゆったりと入浴できるのですが、それも7時半から清掃が入り、ガーガーと大きな音がし出したりで、終了する9時半までは入れ無くなったりします。週2日だけは清掃が無いのですけどね・・
そうであったとしても、やはり是非入りたい温泉です。出たり入ったり何回もしていました。
偶然、この宿の大女将さんとお話する事ができ、80代の大女将さんの肌年齢が、何と何と!驚きの26歳!(測定器が壊れている訳ではなかった)だったり、お孫さんの名前がニマちゃんで太陽という意味だそうで、休憩室には巨大な太陽の絵が飾られていました。大女将さんのパワーがお宿に込められている様な温泉宿でした。次に伺った時もお話させて頂くのが楽しみです。
十勝は食べ物が美味しい所だそうで、北海道を彩るお野菜は勿論の事、帯広では豚丼の店があちこちにあり、私が思ったのはパンが美味しい!やはり十勝産の小麦を使用しているからなのか、有名なますやのパン屋のパンは勿論美味しかったけれど、ローマの湯へ向かう通りにあったパン屋さんのパンも美味しくて、おそらくどのパン屋さんも美味しいんだろうなと思いました。
食べ物が美味しいというのはとても楽しみな事で、帯広へ行く楽しみが増えました。
アクセス的にもpeachで釧路空港まで飛ぶと、発着に合わせて十勝川温泉行のバスが出ていますので、思ったよりとても簡単に本物のモール泉に出会いに行けました。
マトチャン様に教えて頂いたモール泉の事がきっかけで、帯広へ行ってみましたがとっても気に入りました。行って良かったです。有難うございました。
70.帯広・本物のモール泉巡り⑤ホテルボストンに泊まってみた
とにかく温泉重視という事で、尚且つ宿泊価格が川内高城温泉と同様に安く、素泊まり税込み2800円という超安価に惹かれて、口コミ評価が低いのを覚悟で泊まってみたのがホテルボストン。
この宿は、洋室、和室、マンションタイプという3タイプの部屋があり、この際、一番安い部屋でと言ったら和室が当てがわれた。
う~ん流石の古い部屋である。壁紙のシミ、破れは勿論の事。けれどもっと酷い部屋にだって泊まった事がある私は、虫以外のこんな事ではめげない。
この価格で、トイレ、洗面所、冷蔵庫、石油ファンヒーター、丹前以外のアメニティは完備されているという断トツお値打ち価格の宿であるのだ。
浴衣の帯がなかったり、ポットが無かったりしたが、言えば快く持って来てくれたし。
部屋に沁み付く煙草の匂いがきついが、何とか我慢しよう。
アラ❓石油ファンヒーターを付けてしばらくすると突如消えた。臭い匂いが充満するが、しばらくして再点火してみる。だが、またもや煙と共に臭い匂いが充満し消えてしまった。
冬の帯広で、暖房無しで過ごす覚悟は持てなかったので、申し訳なかったけどまた従業員さんを呼んで伝えたら、比較的新しそうな石油ファンヒーターと交換してくれて、朝までもった。初めからこっちにしておいて欲しかったな。
夕方からは御主人が番台に立つ。なかなか話しやすい面白そうな方であったのでつい話しかけてしまった。「何?朝ごはん食べる?じゃあ作ってやるよ」ということでつい700円の朝食を注文してしまった・・あ~やっぱり取り止めようか・・どうせ目玉焼きに千切りキャベツ、漬物と味噌汁・・断れば良かったかなあ・・としばし悩んだりした。ちなみに夕食は1000円で予約注文。
禁煙室は無いらしくどの部屋も煙草臭いらしいが、マンション型の部屋はスポーツ合宿でも使用するらしいので、比較的マシらしい「言えば変えてやったのに」と言われたが今更なので諦めた。次回というのは有るか無いか判らないが、一応頭の隅に置いておいた。
ボストンと言えば温泉、御主人自慢の自家源泉は、広ーい浴槽の真ん中からボコボコと湧き上がっており、黒褐色で肌には微泡がまとわりつくモール泉。香りは玉子臭で味は甘いというちょっと不思議なモール泉。カランもシャワーもモール泉。
そして、何よりも何処よりも床が滑る。とにかく浴室の床が滑って危ないというのがボストンの特徴で、浴槽周りにビニール芝を敷いてくれてあるのだが、無い部分を歩かなければならない事も有るので要注意だ。
大浴場の壁にはレトロタイルも使われていた。
日帰り入浴は7時~23時と長いが、途切れることなく入浴客が訪れている様子で、温泉自体は人気の様であり、御主人は明るい。ドライヤーは無い。
そんなこんなで朝を迎え、朝食タイムとなった。宿泊客は2名だった。
もう一人の方は常連さんであったらしく、私の分まで、盆の上に乗せた朝食を運んでくれた。それを見てびっくり!これが朝食?!煮物から焼き物から、これでもかと言わんばかりに多彩なおかずが盛られ、お盆からもオーバーしてしまった。
当直の御主人が作ってくれた事にも感激~。ちなみに夕食は、大皿に一杯のフライの盛り合わせが山ほどに出るそうだ。
ユニークな御主人にユニークな温泉ホテルと言って良いのかどうか解らないけれど、土曜日1人泊、2食付き最安部屋で税込み4500円!という最強破格値で泊まれる帯広温泉・本物のモール泉の宿なのです。
69.帯広・本物のモール泉巡り④ふく井ホテルに宿泊してみる
宿泊施設は、やはり温泉を優先として考えた時、1つは温泉逍遥様のブログより選ばせて頂いた、ふく井ホテル。
一言で言えば非常に快適でした!
洗練されたデザインの部屋に寝心地の良いベッド。快適な暖房設備と加湿器。
浴室では、見事に山積みにされたバスタオルとフェイスタオルが使い放題。湿ったバスタオルを使いまわす事なく、温泉に入る度に新しいタオルを使えるという贅沢さ。
ブラウン系のシックな浴室には、コーヒーゼリー色のモール泉が美しく掛け流され、湯温は42℃程でヌルトロ。投入口付近には薄茶色の湯華も舞っていました。腐植質4.2㎎のモール泉は、何と自家源泉で24時間入浴OK。
更に、このふく井ホテルは駅前という立地の良さで、到着が遅くなり暗くなっても安心。
ホテル前にはコンビニもありますが、食事の良さには定評があるようです。
そして、女性スタッフの接客対応も親切で、荷物を快く預かって下さり、帯広の共同湯巡りに出かけられました。
帯広駅前にはホテルが林立し天然温泉との看板が見られますが、削掘が禁じられてしまっている現在、ほとんどの宿が運び湯だそうです。
自家源泉を持つ施設としてはこのふく井ホテル他には、共同湯及びたぬきの里や、ホテルボストン等の古くからある施設に限られているそうです。
帯広で本物のモール泉を楽しめ、快適さを重視される方には是非お薦めしたいお宿でした。
68.帯広・本物のモール泉巡り③アサヒ湯・朋の湯・オベリベリ温泉
帯広には大衆浴場が多いが、市内と言っても北海道はでっかい道で、帯広駅から1つの共同湯へ行くにも徒歩で20分、もしくはバスで向かわなければならない。そん中で訪れる事ができた、福の湯以外の3つの源泉かけ流し浴場をご紹介。
①アサヒ湯:観光協会のパンフレットでは、浴槽はレトロタイル風呂であり楽しみに行ったが、リニューアルされ現代のタイルに変わっていた。壁はガラスブロック。ここのモール泉の特徴は、一番の泡付きと一番のヌルヌル感。湯の色は茶褐色であり、湯底からのボコボコ注入も特徴である。湯温も適温で、湯船は小さめながらも、やはり泉質の良いモール泉は気持ち良い。
②朋の湯:昭和56年創業の共同湯だが、浴場の中はレトロとモダンが同居した感じで美しい。何より目立つのは街灯よりも大きく感じる巨大ガラス球の電燈。仕切り壁もガラスブロックだし、カランはバネ式でレトロ感漂うが、柱はパールタイルで、湯縁は大理石というモダンさ。ケロリン桶にはともの湯と書かれていた。湯は40℃程のぬるめで、湯の色も淡い褐色だった。更衣室には懐かしいパーマネント型のドライヤーが置かれていたが健在?かどうかは確かめていない。
③オベリベリ温泉・水光園:此処はタイル風呂では無いが、露天風呂が在るため訪れてみたら、大正解だったのでお伝えしたい。まるでスーパー銭湯さながらジャグジーバスが多くあり、露天風呂も2つあった。中でも大変心地良かったのが、露天風呂に設置されていたジャグジーバスで、頭を置く位置に用いられていたのが発砲スチロール。普通は固くて痛いステンレスの頭部に、発砲スチロールを巻き付けてくれていたのが、ナイスアイデアで有り難かった。
頭も滑らず痛くなく、しかも露天風呂である為ずっと入っていたい気持ち良さだった。
また、サウナも2種類あり私は薬草サウナが気に入った。これら多くの浴槽に全て源泉のモール泉が使用されている。温泉をたっぷり楽しんだ後には、無料休憩所があり、そこで売られていた生乳ソフトクリームのデカイのが何と200円。今時、ソフトクリームもどんどん高くなって450円とかしているのに何という感激価格。う~ん、これら全てが入浴料450円の共同湯料金で楽しめ、外には石臼挽の蕎麦屋さんもあり賑わっていた。帯広観光協会では、帯広バスターミナルからオベリベリ水江園往復のバスチケットが入浴券付き600円で販売されている。 続く・・
画像①アサヒ湯 ②朋の湯 ③オベリベリ水光園
67.帯広・本物のモール泉巡り②ローマノ福の湯
え?ローマのじゃなくてノなの?なんで?と思う帯広温泉共同湯ローマノ福の湯。
隣がローマの泉家族風呂で、1階には美味しいらしい、ローマの泉大衆食堂があり、2階に上がると共同湯があります。入浴料450円は、帯広の何処の共同湯も統一価格のようです。
ローマの家族風呂の方が5年早く営業している為か、完全なレトロタイル風呂でしたが、それに比べ共同湯はやや新しい感じのタイルでしたが、白いタイルだったのがモール泉の色で完全に茶色く変色していました。
源泉は同じぬるめのモール泉で、微泡でヌルヌルし直ぐ泡が付きます。
大きめの浴槽にドバドバ投入される源泉と言うのは、やはり気持ちの良い事と言ったら・・
まあ、隣の家族風呂が小さすぎたためか、改めて大き目の浴槽の心地良さを知った感じがしました。
ここで初めて目にしたのが、温泉成分表にある「腐植質」という文字。コレコレ!探し求めていた本物のモール泉の証。1.0㎎ではありましたが、帯広まで来た甲斐がありました。嬉しくなって写真も。
この共同湯は、畳の無料休憩室も付いています。テレビも有り飲食OKですが、誰も利用されていないので1人で思いっきり寛いでいました。
共同湯の番台の女性の方も優しく「寒く無い?ストーブ入れたら?」等と親切に声をかけて下さったりで、何ともあったかいローマノ福の湯、名前通りでした。
熱いモール泉が多い中で、このぬるいローマノ福の湯の心地良さは、思い出してはまた入りに行きたくなる気持ち良さで、帯広のモール泉では欠かせません。 続く・・
66.帯広・本物のモール泉巡り①ローマの泉家族風呂
本物のモール泉とはどういうものかと、やっと訪れた帯広。
帯広には共同湯が幾つかあるが、レトロタイルを求めてまず向かったのが、ローマ福ノ湯という共同湯らしからぬ名の共同湯の隣にある、ローマの泉家族風呂。
ここは家族風呂・いわゆる貸し切り風呂の個室ばかりがズラッと並んでいる。
大人1人1時間650円という、え?貸切風呂?一般施設の大浴場と同料金で入れる。
他にサウナ付きという貸し切り風呂もあり、こちらは水風呂も付いており値段も高くなるが広い。
部屋は幾つも並んでいるが、料金を払い与えられた部屋番号の温泉に入らなければならない。と言うのも、人数に適した部屋を与えてくれている様だ。
ドアを開けるとレトロなタイル浴室に、長方形の小さな浴槽。縁は余り無い細長レトロタイルで、全体に紺系の渋い色で統一されている。
湯船には黄褐色のモール泉が満たされており、カランからは常時源泉投入されている。
浸かると直ぐ全身に泡付きが有りヌルヌル!
体感的には39℃程の源泉に、1人ゆっくり浸かれる至福。ぬるめでも汗が出て来た。
ローマの泉の源泉は、地下100~数100mから湧き出ているモール泉でとっても新鮮なものだった。泉質名はアルカリ性単純温泉。
他の開いている個室を覗かせて貰ったら、ビーナス像の浴槽もあり、これぞ名にふさわしい感じがする浴室だった。
一体モール臭とはどの様な香りを言うのか?それを知りたかったのもモール泉の本場を訪れた1つであるのだが・・
ローマの湯の建物辺りからは、何だか鉱物臭の様な匂いがしていた。これをモール臭と呼ぶのか?
もっと甘美な香りなのか、はたまた墨の様な香りなのかと期待していた私には良く解らなかったなあ・・。
続く・・
65.番外編―湯治場として活きづく肘折温泉
新庄駅から肘折温泉へ向かうバス停には、まるで老人会の旅行かと思う位に御老人がバスを待ち、村営バスはほぼ満席となり出発して行った。
湯治場として栄える肘折温泉は、そのほとんどの宿が湯治宿(2食~3食付きで6000円台)で、長く連なる温泉街には小さな旅館が軒を並べ、おそらく廃業した宿は無いのではないだろうかと思う。残念ながら店をたたんだ団子屋さんは有るが、玄関を閉ざした宿は見当たらない。
多くの宿がそれぞれに常連客を持つというか、肘折温泉に通う客にはそれぞれお気に入りの宿があるようで、何十年と通い続けている客も多いようだ。
肘折温泉が人を惹きつけ続ける大きな理由として、まず挙げられるのが朝市だろう。
毎年4月下旬GW前頃から、12月の雪が積もるまで1日としてかかさず、夏場は早朝5時半から冬場は6時から、温泉街のほぼ中央、村井若助旅館の前に市が並ぶ。
まだ暗い内から軽自動車の音が聞こえ始め、頬かむりし、腰を曲げたおばさん達が段ボール箱を降ろし、それぞれが持参した商品を並べだす。
ほのかに明るくなった頃、宿の浴衣に丹前を羽織り下駄の音を鳴らして、宿泊客がお目あての品を楽しみにそぞろ出て来る。
季節の旬の物が所狭しと並ぶ市は、その季節季節で楽しみと驚きがある。
春の山菜から始まり、夏場は茹でたとうもろこしや枝豆がおやつになる。秋には地で採れた見事なきのこ。その時々でしかない、決してスーパーマーケットに並ぶ事の無い様な旬の採れたて野菜や、手作りの加工品が並ぶ。四季折々の漬物に、味噌や豆類、手作りの紫蘇巻き、山菜おこわ・・等々挙げればきりがない。年間通じてあるのがちまきでお昼ごはんにもなる。どれもこれも驚く程安くて美味しい。
朝市はバスが通る8時前には店締めとなるが、こういった産直のお買い物、道の駅がお好きな方にとってはとても楽しみなひと時である。
街外れには美味しいお蕎麦屋さんもあった。
そして温泉。現在使用されている組合源泉は2号と5号だそうで、多くの宿がこの組合源泉を使用しているが、4軒程の宿が組合源泉とは別に自家源泉を持っている。このサイトに載っている元河原旅館もその一つであり、熱い組合源泉とぬるい自家源泉を混合して投入している。
今回宿泊した三春旅館もそうだが、特に気に入ったのが日帰り入浴で利用した村井若助旅館の幸の湯。この湯は肘折温泉の草餅色の濁り湯では無く、何と透明で肌に薄く泡ベールが付き、浴感がヌルヌルする。ぬるめの湯は幾らでも入って入たい気持ち良さ。う~んすっごく気持ちいい~次回は是非宿泊したいと決めている。
温泉街の中に古くからある共同湯の大湯の湯船には、お地蔵様が奉られている。キズ湯と言われるこの湯は非常に優しく柔らかい。
情緒や何となく哀愁ある温泉街の風景に欠かせないのが、宿の中でも古くからの建物がそのままで現存している三浦旅館やレトロな郵便局。土産物屋にはこけしが並ぶ。
小さなお宿それぞれが個性を出し合い、亀屋旅館には亀が飾られたレトロな障子がある部屋があり、西本屋旅館にはレトロモダンな金魚の電燈があったりする。
温泉街のイベントとして、装飾電燈が軒先に飾られ情緒を盛り上げる。
冬に出会った田舎町で行われていた雪だるまイベントと小さな冬花火。
夏には大好きな棚田で行われた蛍火コンサート。
最近はスカイランタンイベントも行われているようで、それも楽しみである。
小さな田舎町の小さな手作りイベントであるからこそ、ほのぼのとした温かさがあり、懐かしさやどこか郷愁の様な思いを持つのかも知れない。
初めて肘折温泉に来て初めて泊まったのが亀屋さんだった。選んだのはレトロな障子と格安の料金が決め手だったけれど、あの冬の寒い日、女将さんののんびりした優しさに癒されたのだった。
連泊した時、部屋にそっと差し出される三食の食事と、1日1回だけそっと交換しに来られるストーブの灯油缶。ストーブの上にはやかんが載せられ蒸気を上げていた。そんな部屋でマイ温泉の様に自由に温泉に浸かり、気ままに寝ていたのだった。
この時、肘折温泉の温かさを知り、それから何度か訪れている。違った宿にも宿泊してみている。
肘折温泉街の裏には川が流れ、桜の木も何本か見かけた。大好きな桜の時期にもきっと訪れてみたいと思う。秋には、肘折温泉に訪れるロードから紅葉が美しいだろう。雪を被った月山も見えていた。
何故かふと恋しくなり、無性に温もりを求めたくなる肘折温泉。イベントの時期も良いがそれ以外の季節も、きっと何か伝わるものがあるかも知れない。
64.肘折温泉、三春屋に泊まってみた・・
肘折温泉には自家源泉を持つ宿が何軒か在り、その中の1軒で昔のままのタイル壁が残っている三春屋旅館に連泊してみたが・・
チェックインの時間まで他の温泉で過ごし、宿泊先本館の玄関口で声をかけるが呼べども呼べども誰も出て来ず、別館の方へ行ってみた。
そこでも誰も出ず、ベルがある事に気づき押したら、やっと出て来られた御主人が怒った様に「あっちにもベルがあるから押して下さい」と言われ、また本館へ戻りア~これかとベルを押す。
女将さんらしき人がやっと出て来られ不愛想に部屋を案内するが、階段を3階まで上がらなければならないのだが、一切荷物の事はおかまいなし。
部屋に置かれていたファンヒーターは1日500円かかるそうで、どうしようかと迷っていたら「外へ出しときますので要ったらまた言って下さい」と廊下へ撤去されてしまった。
恐る恐る入ってみたトイレは何とウォシュレットでホッとした。
しかしだ、トイレの屑入れにペーパーが既に溜まっている・・チェックインの時間だが掃除がされていない?このペーパーはいつ除去されるのだろうか?
と思いながら連泊したが、結局チェックアウト時でもそのままで、ゴミが溢れんばかりに積み上げられていった。
温泉メインで泊まった宿であったが、何故御主人はあんなに怒った様な態度なのだろうか?嫌々宿を経営しているのか?本当は閉業したいのだがそれも出来ずに渋々続けているのではないだろうか?それとも、失礼だが何か性格に問題があるのだろうか?等など思い巡らしてみる程、怒った顔と荒っぽい言動が不思議で仕方なかった。
食事は部屋に運ばれて来るが、ドンドンドンバン!とテーブルに乗せられる。ポット交換もひったくるように持って行ってしまった。一切話しかける事ができないあの態度・・
一体どうしたのだろう?何に怒っているのだろう?
肘折温泉に暖かみを求めて来た私としては、連泊を後悔したが今更キャンセルもできないし・・
この状態ではバスタオルは交換して貰えないのではないだろうか?冷めて行くポットの湯は?色々心配になってくる・・
勇気を出して思い切って言ってみたら「言って下さい!言ったら交換しますから」と怒った顔で言われたが、交換して貰えたのだった、ほっ・・。
ちなみに浴室のボロタオルで作られた床マットだが、チェックイン時から既に使用されていた物が置かれていたが、このマットも連泊後のチェックアウトまで交換される事は無かった。
清算に出て来られたのは不愛想な女将さんで、電話予約で1泊2食6000円と言われていたのは税抜き価格で、結局6750円となり他に多くある湯治宿に比べ決して安い訳では無い。
料理は、それなりに温かく運んでくれ悪くは無かった。
最後になってしまった温泉だが、三春屋本館は2つの浴室に、それぞれ泉質が若干違う温泉を持ち、3階に在る方は組合源泉を使用しており、浴槽周りのタイル壁が、紺色の渋い昔から使われていたレトロタイルのままになっている。
暗い浴室には湯滝の音だけが響く。組合源泉であり加水もされているが、非常にパワーを感じる男性的な温泉だ。
もう1つの1階にある温泉が自家源泉で、こちらは金気臭が強く鉄イオンが多く含まれている。溢れ出た温泉が、非常に綺麗なザラザラした鉄錆色の床を創っている。
炭酸イオンも多く浸かるとピリピリした感じがし、高温泉で泡付きは無いが、ぬる湯だったらかなりの泡付きがあるだろうと思う。
浴感はキシキシ感がし、流石鉄分が多いため凄く温まり汗が出る。
こちらの浴室もレトロタイル壁が一部残っているが、御影石の壁にリフォームされてしまっていた。
どちらの温泉も非常にパンチ力があり、寒い季節には持って来いの温泉ではあるだろう。
びっくりした宿だったが、温泉自体は素晴らしく力強いので、肘折温泉に来た際には是非日帰り入浴では味わって欲しい温泉だ。
63.山形・羽根沢温泉松葉荘の白いタイル風呂
以前のこのサイトの掲示板で教えて頂いた、羽根沢温泉松葉荘。その時はサクランボの季節に伺い、サービス、コスパの良さとお料理に感激したのを覚えています。
松葉荘は今や、知る人ぞ知るのお湯の良さとサービスで高評価のお宿。
今回は真っ白なタイル風呂を訪ねて行ってみました。
松葉荘のタイル風呂は50年程前のものだそうで、小さなレトロタイルでは無いのですが、そのマットな白さと大き目の角タイルにレトロ感がありました。
そして、計算されて創られたかのように、透明な湯の色は硫黄成分のためか綺麗な淡いグリーン、その湯を包む白いタイルと、それらの湯船をまとめる焦げ茶色に変色した床板がベストマッチし、小さいながらとても素敵な浴室でした。
あと贅沢言えば、仕切り壁がガラスブロックであれば雰囲気最高なのになあ。
羽根沢温泉は100年程前に石油採掘工事中湧出した温泉で、そのためか微かな油臭があります。浴室に入り、あ~この匂い、どこかの温泉で嗅いだ匂い・・そう鳴子温泉。
東鳴子ほど強烈な油臭はしませんが、いい匂いに感じる位の油臭を持ち、ph.8.5以上にヌルヌル感ある、含硫黄・ナトリウム・炭酸水素というベストコンビの温泉は素晴らしく、寒い季節にも非常に良く温まる、癖になる極上湯でした。
もう1つ感激したのが、女将さんの自然体の親切さ。
山形弁「~にゃあ」で話される女将さんは、寒くて眠れないかと心配だったと言ってくれましたが、とんでもない。エアコンにファンヒーターを用意して下さってましたが、どちらも付けず良く眠れました。
と言うのも驚きの寝具。マットレス+敷布団2枚+ボアシーツ+羽毛布団2枚という豪華な6重の寝具に包まれ、その心地良さに大感激でした。
女将さんメインのお宿は、館内至る所に観葉植物が飾られ、アロマが置かれ、やはりどこか小奇麗にされており、そして何より女将さんの親切は、男性陣にも好感度抜群だろうと思います。
3軒在る羽根沢温泉のお宿の中でも、お湯良し、料理良し、コスパ良し、サービス良しの松葉荘は、断トツ人気なのだろうなと。
ビジネスプラン1人泊税込み8600円でした。
羽根沢温泉は、1軒の共同湯と3軒のお宿が在りますが、源泉の湧出箇所は1つのみで、湧出口に一番近いのが松葉荘だそうです。だから湯が加温無しの適温状態で新鮮・素晴らしいのですね。私も教えて頂いた松葉荘ですが、今回は私からも是非お勧めです。
11月上旬は紅葉が美しい所でもあるので、来年はその時期に伺いたいな、冬もいいだろうな、サクランボの時期も良かったなと思いを巡らせております。